食品安全規格の種類一覧!ISO・HACCP・FSSCなどを解説

マネジメントシステムの認証規格 の中では、品質・環境マネジメントシステムがメジャーですが、食品関連のマネジメントシステム規格も非常に多くの種類があります。
いずれの規格も食品安全性の向上を目指しますが、それぞれ取り組む内容は大きく異なります。そのため、取得前には各規格を比較し、自社に適した規格を選定することが大切です。
そこで、この記事では食品関連のマネジメントシステム認証規格の主な種類として、ISO22000・HACCP認証・FSSC22000・JFS規格・SQFについて解説します。
目次
食品安全に関する認証規格の種類
ここでは、食品安全に関する主な認証規格の種類について解説します。
ISO22000
ISO22000とは、スイスのジュネーブに本部を置く国際標準化機構であるISOによって策定された食品安全マネジメントシステムに関する認証規格です。
品質マネジメントシステムの規格であるISO9001と国際的に有名な食品衛生管理の手法であるHACCPの両方を組み合わせて、企業の自主的な食品安全の取り組みを支援する目的で規格が策定されました。
ISO22000は中小企業であっても認証を取得しやすいように構成されており、他のメジャーな食品安全マネジメントシステム規格と比べて取得しやすいのが特徴です。
取得しやすいからといって安全性に大きな欠陥があるわけでもなく、世界的に認められている規格であるため、取得する価値は十分にあるでしょう。
FSSC22000
FSSC22000とは、ISO22000に要求事項を追加し、より厳密な食品安全マネジメントシステムの構築・運用を目指す規格としての位置づけをもつ認証規格です。
GFSI(Global Food Safety Initiative)からベンチマーク規格の一つとして承認されるなど、高い信頼性を持っています。
FSSC22000は日本でも広く普及している食品安全マネジメントシステム規格であり、アメリカや中国でも認証取得数が多い規格であるため、国内外で認証取得のメリットを享受できる規格といえます。
JFS規格
JFS規格とは、日本食品安全マネジメント協会によって策定された日本発の食品安全マネジメントシステム規格です。
日本食品安全マネジメント協会は、アサヒグループホールディングスやセブン&アイホールディングス、日本ハムなどの企業によって設立された組織であることから、日本国内ではメジャーな規格の一つです。
規格は以下のように3段階に分かれています。
- JFS-A規格:一般衛生管理レベル
- JFS-B:HACCPの実施を含む衛生管理
- JFS-C:国際取引に使われるレベルを想定した衛生管理
JFS-C規格の一部はFSSC22000やSQFと同様にGFSI承認スキームのため、国際レベルでの食品安全マネジメントシステムを求める規格ではありますが、FSSC22000やISO22000のような「国際規格」ではありません。
海外展開を狙うのであれば国際規格として名のしれた認証取得を目指すのが無難といえます。
SQF
SQF(Safe Quality Food)とは、1994年にオーストラリア政府によって策定され、2003年には米国・食品マーケティング協会が所有・運営を行っている規格です。こちらもGFSI承認スキームのひとつです。
SQFもJFS規格同様に以下のように3段階のレベルに分けられています。
- レベル1:基礎レベルの認証
- レベル2:食品安全を対象とした食品安全システム
- レベル3:食品安全と品質システムの認証
HACCP認証
HACCP認証とは、地方自治体や民間企業、業界団体などが審査を行うHACCPに関する認証システムです。
HACCP認証の種類は数多くありますが、日本国内で提供されているHACCP認証は本来のHACCPが求める衛生管理レベルからかけ離れている可能性があります。
また認証団体に拠って、求められる基準がバラバラな点も挙げられます。
そのため、現時点ではHACCP認証の取得はあまり有効な企業戦略とはいえないのが実情です。

どの認証規格を取得すべき?判断すべきポイントとは
さまざまな食品関連のマネジメントシステム規格について解説しましたが、これらのマネジメントシステム規格の中で、どのマネジメントシステム認証を取得すべきなのでしょうか。
ここでは、どの規格を取得すべきか迷った場合に、判断材料となるポイントについて解説します。
取引先のレギュレーションに準拠している規格
食品安全における認証規格の取得が、「取引をはじめるための条件」もしくは「優位に取引を進められる可能性」につながるケースが増えています。
こうした傾向はHACCPの義務化とともに徐々に増えており、今後も食の安全に対する企業の責任が求め続けられる限り続くでしょう。
そのため、まずは現在の取引先から取得を求められている規格があるかどうかを確認してみることが大切です。
会社の方針に適している規格
食品安全における認証規格と、長期的な会社の方針が一致しているかを確認しましょう。
例えば、海外展開を目指している企業には、HACCP認証の取得はあまり適していません。義務化されている国が多いHACCPだけでは、優位性の獲得や取引条件を満たせない可能性が高いためです。
また、家族経営で地元密着型の飲食店には、FSSC22000の取得はあまりおすすめできません。小規模な企業であるのに厳密な管理をするのは手間やコストの点から考えて非効率的であるためです。
このように、規模や今後の展望に応じて最適なマネジメントシステムは異なります。そのため、会社の方針に適した規格かどうかを確認しましょう。
ISO・FSSC・JFS規格の認証取得企業数

ここでは、ISO22000・FSSC22000・JFS規格の認証取得企業数を解説します。
ISO22000の取得企業数
ISO22000の認証取得組織数は、公益財団法人「日本適合性認定協会」のホームページから検索できます。
2025年2月17日現在、日本国内では1,358件の組織がISO2200を取得しています。その中には、「アイリスオーヤマ株式会社」「アサヒビール株式会社」「カルビー株式会社」などの有名企業の事業部や工場も含まれています。
FSSC22000の取得企業数
FSSC22000の認証取得組織数は、FSSCのホームページから確認できます。
2025年2月17日現在では、世界全体の認証取得数が37,539件で、日本国内では3,412件です。その中には、「エースコック株式会社」「味の素株式会社」「ブルボン株式会社」などの有名企業の事業部や工場も含まれています。
JFSの取得企業数
JFSの認証取得企業数は、一般財団法人「食品安全マネジメント協会」のホームページから確認できます。
2025年2月17日現在、日本国内では2,716件の組織がJFSを取得しています。具体的な企業名は検索できませんが、多くの企業が認証を取得しています。

食品安全に関する規格を取得するメリット

ここでは、食品安全に関する規格を取得するメリットを解説します。
食品関連のリスク軽減や事故の予防につながる
各規格の目的でもある食品安全性を向上させる過程で、食品関連のリスク軽減や食品事項の予防が期待できます。
例えばISO22000であれば、食品安全マネジメントシステムを構築する過程で、自社の製造プロセスにおけるリスクを明確化したうえで、管理するための具体的な方法を策定します
業務効率化につながる
各規格を取得する過程で、業務プロセスを可視化することが求められます。ムダな作業や非効率的な方法が発見されれば、改善することで業務効率化が期待できるでしょう。
また何かしらの問題が発生した場合にもマニュアルやルールを明確化する必要があるため、スピーディーな対応につながります。その結果、問題への対応にかかる工程も削減できるのです。
取引先や顧客からの信頼を獲得できる
各規格を取得することで、自社の食品安全に対する姿勢を取引先や顧客にアピールできます。
規格を取得することは、「自社の食品安全に対する取り組みが、その規格の基準を満たしている」という客観的な証明になるため、信頼の獲得につながります。
まとめ
この記事では、食品安全に関する認証規格として、ISO22000・HACCP認証・FSSC22000・JFS規格・SQFについて解説しました。
各規格の取り組み内容は異なるものの、食品安全の向上を目指している点は一致しています。そのため、自社においてどの規格を取得するかは、「取引先からの要求」や「経営方針とマッチしているか」といった点を確認したうえで選定すると良いでしょう。
ISOコンサルタントに相談することで、自社に適した規格を提案してくれます。各規格の不明点がある場合には、自社だけで答えを出すのではなく、ISOコンサルタントに相談することも一つの手といえるでしょう。

ISOプロでは御社に合わせたHACCP・ISO22000取得・運用支援を実施中
ISOプロではHACCP、ISO22000、FSSC22000、JFSなどの各種食品安全規格の認証取得から運用まで幅広くサポートしております。
また、マニュアル作成など御社に合わせたムダのない運用を心がけており、既に認証を取得しているお客様においてもご提案しております。ぜひご相談ください。
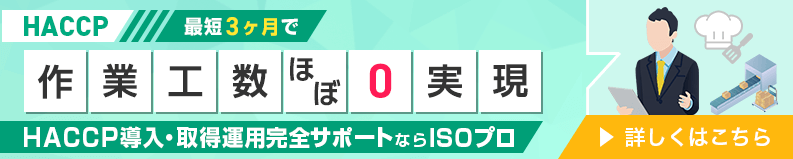




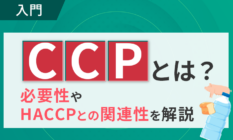

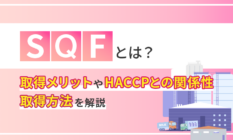




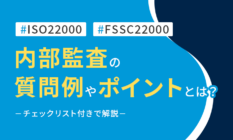








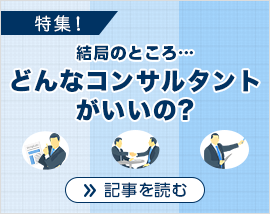

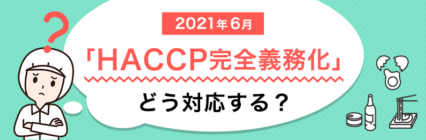
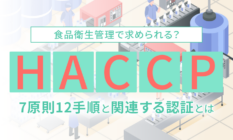










こんな方に読んでほしい