JIS規格とは?概要や目的、ISO規格との違いを解説

- JISとは日本産業規格の略称
- JISはISO規格を日本語訳したもの
- 各マネジメントシステムの規格群もJIS規格という形で日本語訳されている
日本においては、JIS規格が要求事項として認知されていますが、これらはISO規格とどのような違いがあるのでしょうか?
ISO(国際標準化機構)が制定するISO規格の原文は英文のため、日本語に翻訳したものをJISとして発行しています。
ISOの普及を推進する目的で翻訳され、基本的にISOと同様のものとして扱われています。
この記事は、JIS規格について解説していきます。
目次
JIS規格とは

JIS(Japanese Industrial Standard:日本産業規格)とは、産業標準化法に基づいて制定される自動車や電化製品、情報処理サービスなどに関する国家規格です。
JIS規格にあまり馴染みのないという方も、商品にJISマークが表示されているのを見たことがある方もいるかもしれません。JISマークを表示することで、JIS規格を取得していることを取引先や消費者にも直感的に伝えることが可能です。
JIS規格の制定や改正における審議などは、JISC(Japanese Industrial Standards Committee:日本産業標準調査会)が行っています。
またJISCは、ISO(国際標準化機構)やIEC(国際電気標準会議)に日本で唯一の会員として参加している機関でもあります。
JIS規格を取得するには、第三者機関(登録認証機関)による認証を受けることが必要です。
規格とは
そもそも規格とは、製品・サービスやマネジメントシステムなどを標準化するために定義された「決まりごと」「基準」を文章化したものです。
また標準化とは、例えば製品の形状や寸法、成分、性能などを統一し、製品の互換性や品質、安全性を確保し、利便性を向上することです。
規格は地政学的に以下の4つの種類に分類され、JIS規格は国家規格に該当する規格です。
- 国際規格:世界中で利用されている規格(ISO規格やIEC規格など)
- 地域規格:ある地域の国々で利用されている規格(EN規格など)
- 国家規格:基本的に国内で利用されている規格(JIS規格など)
- 地区規格:業界内や企業内で利用されている規格
JIS規格の必要性
JIS規格は、なぜ必要なのでしょうか。
JIS規格の必要性を考える際にわかりやすい例に、トイレットペーパーのサイズがあります。
実はトイレットペーパーのサイズはJIS規格によって114mmと定められています。
トイレットペーパーのサイズに標準となる基準がないとどうなるでしょうか。
各メーカーが自由にサイズを決めて製造するため、「商品によってホルダーに取り付けできなくなる」「ホルダーに応じて商品のサイズを変更する必要が出てくる」「ホルダーに取り付けできない場合、顧客満足度が低下する」といった不具合が生じるでしょう。
つまり、標準となる基準がないと不便さや業務のコスト増などの課題が発生してしまうのです。こうした事態を防ぎ、生産の効率化や利便性・公平性を確保するといった観点から、JIS規格は欠かせないものであるといえるでしょう。

JIS規格の成り立ち

JIS規格の前身である日本標準規格は、先進資本主義国における標準規格制定の流れもあり、工業品統一調査会によって1920年代に制定されました。第2次世界大戦中には軍需品調達との兼ね合いもあり、物資の有効利用を図る臨時日本標準規格や日本航空機規格などが規格化されています。
第2次世界大戦が終了したのち、工業品統一調査会が廃止した代わりに、日本工業標準調査会(JISC)が設置されました。そして1949年に施行された工業標準化法に基づき、日本工業規格が制定されました。
その後、2019年の工業標準化法の改正により、「日本産業規格」に変更。併せて日本工業標準調査会も「日本産業標準調査会」と現在のJIS規格へ形を変えたのです。
JIS規格が活用されている製品例

JIS規格は膨大な数の規格があるため、製品・サービスごとに部門を設けており、アルファベットと分類番号で表しています。以下に、部門記号をまとめました。
- A:土木及び建築
- B:一般機械
- C:電子機器及び電気機械
- D:自動車
- E:鉄道
- F:船舶
- G:鉄鋼
- H:非鉄金属
- K:化学
- L:繊維
- M:鉱山
- P:パルプ及び紙
- Q:管理システム
- R:窯業
- S:日用品
- T:医療安全用具
- W:航空
- X:情報処理
- Z:その他
それでは実際にどのような製品にJIS規格が活用されているのでしょうか。ここでは、JIS規格が活用されている製品例を紹介します。
靴
私たちが着用している靴のサイズ(JISS5037)もJIS規格です。サイズの測定方法やサイズ表記の規定があります。
また、安全靴(JIST8101)や革靴(JISS5050)にもJIS規格があります。性能における安全性や強度などにおいて基準が設けられています。
非常口
街中でよく見る非常口のマークもJIS規格です。一目見るだけで誰もが非常口の場所を理解できるようになっています。
このマークは案内用図記号(ピクトグラム:JISZ8210)と呼ばれており、非常口以外にもトイレやエレベーター、身障者用設備、喫煙所などさまざまなピクトグラムがJIS規格として定められています。
QRコード
最近ではさまざまなデータ取得や送信の手段として活用されているQRコード(JISX0510)も規格化されています。QRコードのシンボル体系の特徴やデータキャラクタの符号化などが規定されています。
カーバッテリー
国産自動車のカーバッテリーには「55B24R」などのJIS規格が表示されています。これは、始動用鉛蓄電池(JISD5301)に規定されているものです。国内外にさまざまな規格があるため、カーバッテリー自体に表記することで、交換する際に確認しやすくなっています。

JIS規格を認証取得する方法

JIS規格を取得するには、JISマーク表示制度に則って、国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)による認証審査に適合し、認証されることが必要です。以下にJIS規格を認証取得する手順をまとめました。
- 登録認証機関に審査を依頼する
- 工場審査及び製品試験を受ける
- 問題なければ認証が決定する
- 認証における手続きを実施する
- 認証完了
一般的に、申し込み~認証完了までにかかる期間は3~4か月程度です。ただし、具体的な期間や費用は、製品や規格によって異なるため、登録認証機関に問い合わせましょう。
またJIS規格の認証後は、JISマークの使用に関する契約書を締結することでJISマークを製品に表示できます。
JIS規格とISO規格の違い
ここでは、JIS規格と混同しやすいISO規格との違いについて解説します。
ISO規格とは
ISO(国際標準化機構:International Organization for Standardization)とは、ISO規格を運用する非営利法人の名称です。170を超える各国の国内標準化団体で構成されており、日本からはJISCが参加しています。
ISO規格とは、「国際間の取引を円滑化し、国際貿易の発展を支援するために発行されている世界的な共通基準」のことです。
つまり、先ほど解説したトイレットペーパーのサイズと同じ考え方を、国同士の輸出入において行っているのがISO規格といえます。各国が独自に定めた基準を商品に採用しており、両者の基準が異なる場合には、輸出先の国の基準に合わせた輸出用の商品を新たに製造する必要が出てくるのです。
こうした国際間の取引を円滑化しているものがISO規格であることから、多くの国の多種多様な業種において、ISO規格が取得されています。
代表的なISOマネジメントシステム規格には、ISO9001やISO27001、ISO14001などがあります。ISO規格の詳細は、以下の記事をご覧ください。
JIS規格とISO規格の関係性
JIS規格とISO規格の関係性は、基本的には「ISO規格を翻訳したものがJIS規格」であることです。
というのも、ISO規格は基本的に英語で策定されることが多く、日本語では原文が作成されていません。そのため、日本でISO規格を普及させるにあたって、日本語に翻訳したものをJIS規格として発行しているのです。
翻訳されたJIS規格は国際整合化が図られており、基本的にはISO規格と同様のものとして扱われています。
例えば、ISO9001には日本語に訳したJIS Q 9001があります。JIS Q 9001を取得すると、ISO9001を取得したことになるのです。
JIS規格とISO規格の違い
JIS規格とISO規格の違いを以下にまとめました。
- ISO規格は世界的に有効な国際規格、JIS規格は日本でのみ有効な国家規格
- ISO規格にはマネジメントシステム(組織活動におけるリスクを管理する仕組み)に関する規格があるが、JIS規格は製品に関する規格のみが発行されている
- JIS規格のみ、製品に記載できる認証マーク(JISマーク)がある
- ISO規格とJIS規格では、ねじや紙、繊維などの寸法が異なる製品がある

JIS規格に対応しているISO規格を検索する方法

JIS規格は、ISO規格を含めた国際規格と整合性を図っています。そのため、基本的にはJIS規格と対応したISO規格が存在します。
例えば、クレジットカードなどのサイズについて定めたJIS規格は、「JISX6301」ですが、ISO規格の「ISO/IEC7810」に対応しています。
しかし、JIS規格に対応したすべてのISO規格を一つひとつ検索するのは手間がかかります。そこで、JIS規格と対応したISO規格を検索する方法を以下にまとめました。
- JISCホームページの「JIS・国際規格の整合性情報(外部リンク)」ページを開く
- 検索したいJIS規格の番号もしくはISO規格の番号を入力する
- 一覧表示ボタンを押す
3ステップで知りたい規格にたどり着けるため、非常に便利です。JIS規格と対応したISO規格を検索したい場合には、利用してみてください。
JIS規格やISO規格を取得するメリット

それでは、最後にJIS規格やISO規格を取得するメリットを解説します。
製品・サービスの品質や技術が向上する
JIS規格やISO規格を取得するためには、規格が要求する基準に自社の体制が適合しなければなりません。規格が求める基準を満たすための方法が、各規格の要求事項として示されています。
取得を希望する組織は、要求事項に沿って自社の体制を構築・運用することが必要です。
そうした取り組みの中で、品質や技術を管理する方法や手順が明確になり、従業員の意識も高まっていくため、製品・サービスの品質や技術の向上につながるのです。
取引先や顧客への信頼を獲得できる
JIS規格やISO規格を取得できたということは、自社の体制が「国内的な基準」や「国際的な基準」に達していると、審査機関から認証されたという証明になります。
そのため、取引先や顧客は安心して自社の商品・サービスを購入できるでしょう。
2013年にJIS認証取得事業者を対象としたJISCBA(JIS登録認証機関協議会)の調査(外部リンク)によると、アンケート回答者の80%がJIS認証の取得が「対外的な信用度の向上」に効果があったと回答したとのことです。
また、ISOプロが約1,000人のIT系企業の経営者・経営幹部に行ったアンケート調査(外部リンク)によると、ISO27001(情報セキュリティに関する規格)を取得していないSaaS系ツールの導入は消極的になるか?という質問に対し、66%の回答者が「はい」と回答しました。
この2つのアンケート調査からわかるように、JIS規格やISO規格の取得は、取引先や消費者に信頼感を与えられるでしょう。
海外からも信頼を得られる
ISO規格は国際規格であるため、事業のグローバル化を検討している企業やすでに海外展開している企業は、ISO規格の取得は取引において信頼を得られるでしょう。
一方、JIS規格は国内規格であるものの、先ほどのJISCBA(JIS登録認証機関協議会)の調査によると、以下のような回答が得られています。
- 中国、東南アジアにおいて、日本製品に対する信頼が高く、JIS認証で高品質の製品を確保できると考えられている。
- 特に鉄鋼製品等において、自動車や家電など、日本企業の海外トランスプラントが関わってJISマーク品の需要を喚起している。
- B7501精密水準器・B7512鋼製巻尺等の測定機器、M7624安全帯等の安全用具、B2061給水栓・S2400陶磁器製耐熱食器等の飲食に影響する製品等については、JIS認証の取得、JISマークの表示がアジアへの輸出に有利となるケースがある。
このように、アジア圏への進出においてはJIS規格も信頼を得られる可能性があります。

まとめ
この記事では、JIS規格の概要やISO規格、IEC規格との関係性を解説。また、JIS規格やISO規格を取得するメリットも紹介しました。
JIS規格やISO規格を取得することで自社の製品・サービスや体制が基準に達していることを証明できます。そのため、国内外における市場の優位性を高めたい場合には取得がおすすめです。
「自社において、どの規格が適しているのかわからない」という場合には、プロのコンサルに依頼してみるのも一つの手といえるでしょう。

ISOプロでは月額4万円から御社に合わせたISO運用を実施中
ISOプロではISO各種の認証取得から運用まで幅広くサポートしております。
また、マニュアル作成など御社に合わせたムダのない運用を心がけており、既に認証を取得しているお客様においてもご提案しております。
サポート料金においても新プランを用意し、業界最安級の月額4万円からご利用いただけます。
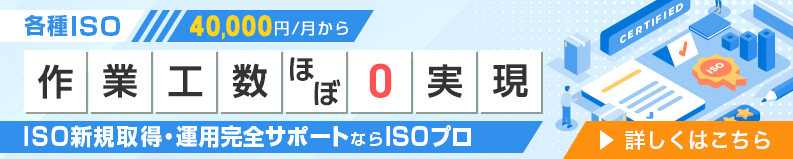




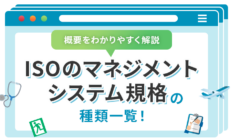



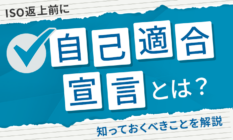

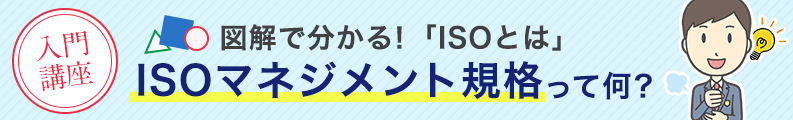





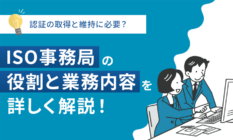
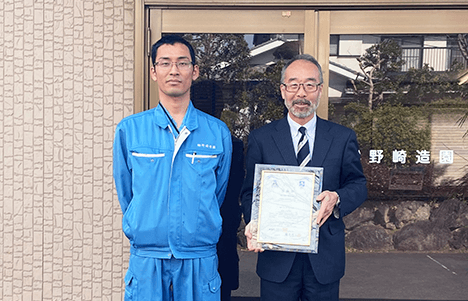
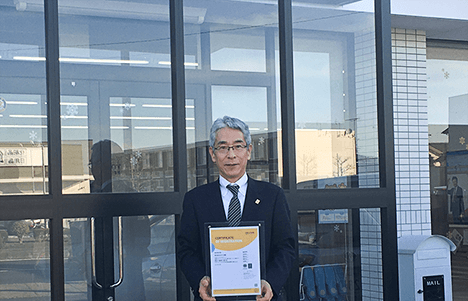
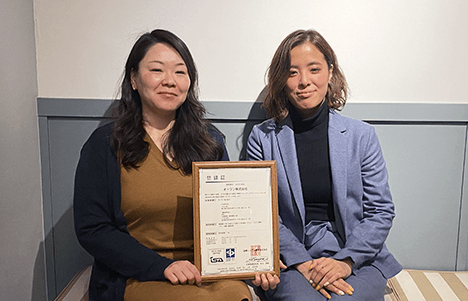



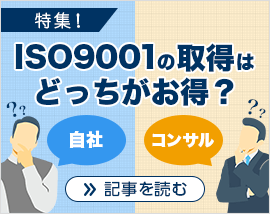










こんな方に読んでほしい