Pマークに違反するとどうなる?違反のリスクや正しい対応を解説

プライバシーマーク(Pマーク)を取得している企業の中には、「本当にうちの運用は大丈夫だろうか」「うっかりミスで違反にならないか心配」と不安に思われる方も多いかもしれません。Pマークは、個人情報保護マネジメントシステム(PMS)をもとに、適切な個人情報管理を行っていることを示す大切な証明です。
しかし、プライバシーマーク付与事業者が個人情報の取り扱いを誤れば、認証の取り消しや罰則、信頼の失墜といった深刻な事態を招くおそれがあります。
この記事では、Pマークのルール違反に該当する行為の内容や、違反時に起こる影響、企業が取るべき正しい対応と再発防止策を分かりやすく解説します。社内体制を整え、違反を未然に防ぐための実践的なポイントを知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
目次
プライバシーマーク(Pマーク)のルール違反とは
プライバシーマーク(以下、Pマーク)のルール違反とは、大きく分けて「プライバシーマーク付与に関する規約への違反行為」と「個人情報保護法への違反行為」の2つがあります。
まず、Pマーク付与規約における違反とは、制度上の「事故等」に該当する行為を指します。日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)の定義は下記の通りです。
【プライバシーマーク付与に関する規約における『事故』の定義】運営要領「プライバシーマーク付与に関する規約(PMK500)」(事故等の報告義務)において、「プライバシーマークにおけるマネジメント構築・運用指針への不適合により発生した個人情報の外部への漏えいその他本人の権利利益の侵害」を「個人情報の取扱いにおける事故等」と定義づけています。具体的には以下の事象に該当するものです。
① 漏えい ② 紛失 ③ 滅失・き損
④ 改ざん、正確性の未確保
⑤ 不正・不適正取得
⑥ 目的外利用・提供(ただし書きに該当する場合を除く)
⑦ 不正利用
⑧ 開示等の求め等の拒否(ただし書きに該当する場合を除く)
⑨ ①~⑧のおそれ
引用:日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)「プライバシーマーク制度における「事故」の定義を知りたい。」
引用日2025/11/7
たとえば、誤送信や誤配達による書類の渡し間違い、社内外での情報漏えいや個人情報紛失などが代表的なケースです。実際、JIPDECが発表した2024年度の事故報告集計によると、発生事象のうちもっとも多かったのは「漏えい」で全体の75.8%、次いで「紛失」が9.0%でした。
(出典:日本情報経済社会推進協会プライバシーマーク推進センター「2024年度個人情報の取扱いにおける事故報告集計結果」(外部リンク))
一方で、個人情報保護法の違反とは、法的な観点での不適正な個人情報の取り扱いを指します。具体的には、利用目的を通知せずに個人情報や特定個人情報を取得したり、本人の同意なく目的外利用を行ったりする行為が該当します。また、情報管理を怠った結果、漏えい・滅失・毀損が発生することも違反とされます。たとえば、誤送信や設定ミスによって社外にデータが閲覧可能な状態になるケース、ハッキングによってデータを改ざんされたケースなども含まれます。
【個人情報保護法による報告対象となる事故の定義】漏えい…個人データが外部に流出すること
●該当事例
○書類やメールを誤送付・誤送信した
○設定ミスでインターネット上から閲覧可能になった
○書類や媒体の盗難、不正アクセスにより窃取された
※第三者に閲覧される前にすべて回収した場合や、本人の同意のもと提供した場合は「漏えい」に該当しない滅失…個人データの内容が失われること
●該当事例
○誤って帳票を廃棄した
○社内で書類や媒体を紛失した
※同じ内容のデータが他に保管されていれば「滅失」には当たらない
※適切に廃棄されず流出した場合は「漏えい」となる毀損…個人データの内容が意図せず変更されたり、利用できない状態になること
●該当事例
○ハッキングなどによりデータが改ざん・破壊された
○復元キーの紛失で復号できなくなった
※同一内容のデータが他に保管されていれば「毀損」には該当しない
※ランサムウェアで同時に情報が盗まれた場合は「漏えい」にも該当する
(出典:個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(外部リンク))
【個人情報保護法における不法な利用行為の定義】●利用目的を通知・公表せずに個人情報を取得する
●利用目的をあいまいにしたり、本人が予想できない使い方をする
●本人の同意なしに目的外で個人情報を利用・提供する
●違法・不当な目的のために個人情報を利用・提供する
●差別や偏見を助長するおそれのある形で個人情報を使用する
●不正な手段で個人情報を入手する
●個人情報の安全な管理を怠る
(出典:個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(外部リンク))
Pマークのルール違反は、不正使用など故意に情報を漏らすような重大行為だけでなく、日常業務での小さな不注意からも発生し得ます。「自分たちは大丈夫」と油断せず、日々の運用や社員教育を徹底しましょう。

Pマーク取得企業がルール違反するとどうなる?
Pマークを取得している企業がルール違反を起こすと、社会的にも法的にも大きな影響を受けます。ここからは、違反によって起こり得る主なリスクと影響について説明します。
Pマーク認証を取り消される
Pマークを取得した企業が個人情報を不適切に扱った場合、審査機関から認証を取り消されることがあります。たとえば、個人情報の漏えい・目的外利用・法令違反などが確認された場合は、意図的なものでなくても対象です。Pマーク認証を失うと「情報管理が不十分な企業」という印象を与えるおそれがあります。
個人情報保護法違反の罰則を受ける
Pマークのルール違反が個人情報保護法にも抵触した場合、個人情報保護違反として行政処分や刑事罰が科される可能性があります。たとえば、個人情報保護委員会の報告徴収や立入検査に応じなかった場合には50万円以下の罰金、命令違反には1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められています。
さらに、個人が不正な利益を得ることを目的に、個人情報を提供・盗用した場合は1年以下の拘禁刑または罰金、法人には最高1億円の罰金が科されることもあります。
(出典:個人情報保護委員会「個人情報取扱事業者等が個人情報保護法に違反した場合、どのような措置が採られるのですか。(外部リンク))
社名が公表される
個人情報保護委員会は、法令違反や勧告命令に従わない企業に対し、その事実を公表することができます。社名が公に明らかになると、報道などを通じて「個人情報管理が甘い企業」として世間に知られてしまうおそれがあります。
特に、SNSや口コミを通じた拡散は速く、企業イメージの回復には長い時間がかかります。たとえ故意でなくても、結果的に個人情報の漏えいを起こした場合には社会的制裁を受けることもあります。そのため、個人情報に関する事故が起きた際は迅速かつ誠実な対応が求められるでしょう。
社会的な信頼が失墜する
Pマークは「個人情報を適切に管理している企業」であることを示す信頼の証です。そのため、違反が明らかになると企業の信用は大きく損なわれます。情報セキュリティ対策が甘いために、既存顧客や取引先から契約を打ち切られれば、売上が減少し、経営悪化につながるかもしれません。
また、対応業務の増加による社員のモチベーション低下など、社内にも悪影響が及びます。信頼を取り戻すには長い時間と努力が必要になるため、日頃からルール順守を徹底し、違反を未然に防ぐ仕組みづくりが大切ではないでしょうか。
ルール違反を起こしたときの企業の対応方法
Pマークのルール違反が発覚した場合、対応を誤ると被害が拡大したり、信頼回復が難しくなったりするおそれがあります。ここからは、違反発生後に企業が取るべき具体的な対応を説明します。
速やかに事実関係を調査する
違反が発覚した際は、まず迅速に事実関係を把握することが大切です。どのような違反が起きたのか、個人情報が含まれているのか、漏えいの範囲や量、原因は何かなどを詳細に調べます。
これらの情報が不十分だと、その後の対応や再発防止策に誤りが生じるおそれがあります。特に、外部への漏えいが疑われる場合は、早急な確認と一次対応に取り組みましょう。
再発防止策を策定する
違反の原因を明らかにしたら、同じミスを繰り返さないための再発防止策を立てます。具体的には、社内マニュアルの見直しや従業員への再教育、情報管理ルールの再周知などが挙げられます。
また、違反を起こした当事者に対しては、内容に応じて懲戒処分を行うこともあります。これにより再発を防ぐだけでなく、社内全体へ「情報管理を軽視しない」という意識を浸透させられるでしょう。
Pマーク審査機関・個人情報保護委員会へ報告する
事故や違反が発生した場合は、速やかにPマーク審査機関や個人情報保護委員会への報告が必要です。JIPDECから再発防止策の実施状況報告を求められた場合は、措置通知の受領日から2か月以内に「再発防止策報告書」を提出します。
個人情報の漏えいなど、本人の権利利益を害するおそれがある場合は、約3~5日以内に個人情報保護委員会へ報告し、本人への通知も行わなければなりません。適切な報告を行い、早期対応と信頼回復に努めましょう。
(出典:プライバシーマーク制度「JIPDECへの事故等の報告」(外部リンク))
(出典:個人情報保護委員会「漏えい等報告・本人への通知の義務化について」(外部リンク))

Pマーク取得企業が違反リスクを減らすためやるべきこと
Pマークを維持していく上で、もっとも大切なのは「違反を起こさない仕組みづくり」と「起きたときの備え」です。社内ルールや法令違反を完全にゼロにすることは難しいですが、日頃の対策次第でリスクを減らすことは可能です。ここでは、Pマーク取得企業が取り組むべき3つのポイントを分かりやすく紹介します。
事故を起こさないための体制を作る
個人情報を取り扱う際のルールを明文化し、全従業員に周知しましょう。たとえば、情報の持ち出し禁止・暗号化・アクセス制限といったセキュリティルールを定めます。加えて、個人情報管理システムの更新や業務フローの見直しなどは定期的に行うことが求められます。
従業員に個人情報の取り扱いについての教育を行う
ルールを作るだけでなく、従業員教育を通じて「なぜそのルールが必要なのか」を理解させることも大切です。違反時のペナルティも明確にし、従業員一人ひとりに責任意識を持たせることが再発防止につながります。
事故が起きた場合に備えてルールを作る
万が一事故が発生した際に備え、早期発見と報告方法、緊急対応の手順を明確に定めておきましょう。発生時の報告先やフロー、審査機関・個人情報保護委員会への報告手順、本人への連絡方法を定めておくことで、被害拡大を防げます。
まとめ
Pマークのルール違反は、企業の信用や事業の継続に直結する重大なリスクです。認証の取り消しや罰則といった直接的な処分だけでなく、顧客や取引先からの信頼を失うことで、経営全体に深刻な影響を与えるおそれがあります。
違反を防ぐためには、まず「事故を起こさない体制」を整え、従業員一人ひとりが個人情報保護の重要性を理解し、ルールを順守することが欠かせません。また、万が一の事故に備えた報告・再発防止の仕組みづくりも必要です。日常の業務フローを見直し、情報管理や社員教育を継続的に行うことで、違反リスクを減らせるでしょう。

ISOプロでは月額4万円から御社に合わせたISO運用を実施中
ISOプロではISO各種の認証取得から運用まで幅広くサポートしております。
また、マニュアル作成など御社に合わせたムダのない運用を心がけており、既に認証を取得しているお客様においてもご提案しております。
サポート料金においても新プランを用意し、業界最安級の月額4万円からご利用いただけます。
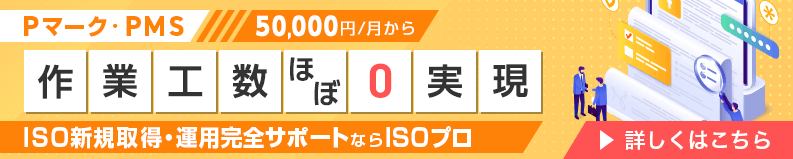










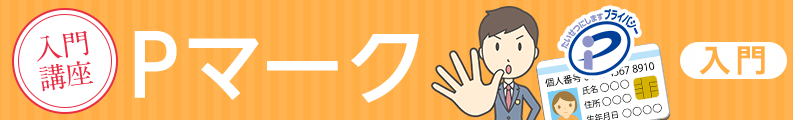


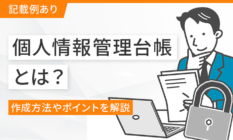



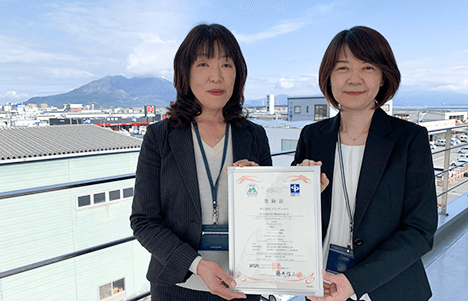

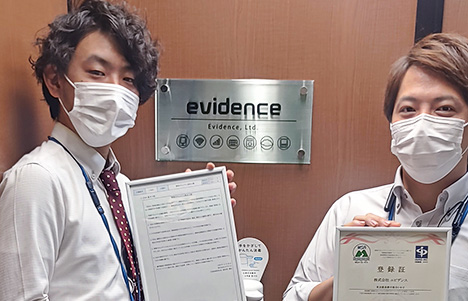


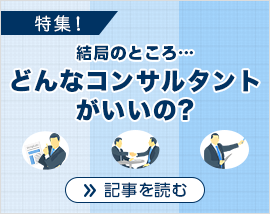














こんな方に読んでほしい