プライバシーポリシーと個人情報保護方針の違いとは?意味と作成すべき方針をわかりやすく解説

- プライバシーポリシーと個人情報保護方針は、目的や対象が異なる
- 両者を適切に使い分けつつ、連携させることが大切
「プライバシーポリシー」と「個人情報保護方針」は、情報セキュリティへのニーズが高まる現代ビジネスにとって欠かせないテーマです。正しく理解し、設定することで企業の信頼性向上につながります。
しかし、両者の意味や使い分けを正しく理解している方は意外と少なく、実際に「どちらを作ればよいのか」「同じ内容でよいのか」といった疑問を持つケースは少なくありません。
そこで、この記事ではプライバシーポリシーと個人情報保護方針の違いを、初心者にもわかりやすく整理します。また、企業が両者をどのように作成・運用すべきかについても解説するため、ぜひ参考にしてください。
目次
個人情報保護方針とは?
個人情報保護方針とは、企業や組織が「個人情報をどのような考え方で保護・管理していくか」を明文化した基本方針のことです。つまり、個人情報保護に関する「理念」や「宣言」にあたるものです。
個人情報保護方針を策定し、公表する主な目的をまとめました。
- 組織全体としての個人情報保護の姿勢を明示すること
- 従業員に対して、情報取り扱いに関する方針・責任を周知すること
- 顧客・取引先などに対して、企業の信頼性を示すこと
社内外に対して意味をもっており、個人情報保護に関する取り組みを行ううえで欠かせない要素といえます。
一般的な個人情報保護方針の記載内容をまとめました。
| 記載内容 | 内容の例 |
|---|---|
| 基本理念・適用範囲 | 個人情報保護に関する企業の考え方、基本的な姿勢、適用される個人情報の範囲 |
| 個人情報保護の原則 | 個人情報のライフサイクル(取得→利用→提供→保管→廃棄)全体の管理に関する基本的な考え方 |
| 法令遵守 | 個人情報保護法など、関連法令や社内規程の遵守 |
| 安全管理措置 | 不正アクセスや漏えい防止など、情報保護のために講じる安全対策 |
| 苦情・相談への対応 | 個人情報の取り扱いに関する相談や苦情の受付体制 |
| 継続的改善への宣言 | 方針や管理体制を継続的に見直すことへの言及 |
PMSとの関連性
PMS(Personal Information Protection Management System:個人情報保護マネジメントシステム)とは、個人情報を適切に管理するためのルール、手順などを定めた仕組みのことです。その中で、個人情報保護方針は、PMSを構築・運用するうえで中核となる要素として位置付けられています。わかりやすくいうと、「自社はどのような姿勢で個人情報を取り扱うか」という、PMS全体の方向性を定めた基本方針といえるでしょう。
そのため、個人情報保護方針をもとに、PMSにおける情報の取得・利用・保管・廃棄などに関する一連の運用ルールや手順を策定します。
また、PMSを第三者が認証する制度に、「プライバシーマーク(Pマーク)」があります。Pマークを取得する際には、個人情報保護方針の策定が義務付けられています。

プライバシーポリシーとは?

プライバシーポリシーとは、企業や団体が個人情報をどのように取得・利用・管理・提供するのかを具体的に示した文書です。一般的には、ホームページやWebサイト、アプリなどで個人情報を取得する際に、利用者へ公開される形で提示されます。
例えば、問い合わせフォームや会員登録、資料請求などでユーザーから名前・メールアドレス・住所などの個人情報を取得する場合、その情報を「どの目的で」「どのように保護するのか」を明記するのがプライバシーポリシーの役割です。
一般的なプライバシーポリシーの記載内容についてまとめました。
| 記載内容 | 内容の例 |
|---|---|
| 取得する情報の種類 | 氏名、住所、電話番号、メールアドレス、アクセスログなど |
| 利用目的 | 問い合わせ対応、サービス提供、マーケティング分析など |
| 第三者提供の有無 | 外部委託や共同利用の有無とその範囲 |
| 管理体制 | セキュリティ対策、委託先の監督など |
| 開示・訂正・削除の手続き | ユーザーが自分の情報を確認・修正できる方法 |
| クッキー(Cookie)などの技術利用 | Webサイトでクッキーやアクセス解析ツールなどを利用する場合、利用目的や設定変更の方法など |
| 問い合わせ窓口 | 個人情報に関する相談・苦情の受付先 |
このように、プライバシーポリシーは利用者に対する説明責任を果たす文書であり、企業の情報管理の透明性を高めるために欠かせない取り組みの一つです。
プライバシーポリシーの詳細やPマークとの関連性は、以下の記事をご覧ください。
個人情報保護法との関連性
個人情報保護法では、個人情報取扱事業者に対して、利用目的の特定・公表、適正な取得、第三者提供の制限、開示請求への対応など明確なルールが定められており、「公表等」義務が課せられています。こうした説明義務を果たすための手段として、プライバシーポリシーがあります。
特に2022年の法改正以降、企業には「個人情報の取扱いを明確にし、本人に通知または公表する義務」が強化されました。そのため、プライバシーポリシーを策定・公開していない企業は、法令違反に問われる可能性もあります。
つまり、プライバシーポリシーは法令遵守のための欠かせない宣言であり、同時に顧客・ユーザーとの信頼関係を築くための土台ともいえます。
個人情報保護方針とプライバシーポリシーの違い
ここでは、個人情報保護方針とプライバシーポリシーの違いを「情報の範囲・対象者」「法的要件」「記載内容」の3つの観点から解説します。
情報の範囲・対象者
個人情報保護方針は、企業全体が扱う個人情報を包括的に対象としています。そのため、社員・取引先・顧客など、あらゆる関係者の個人情報が管理対象となるのが特徴です。
一方、プライバシーポリシーは主に顧客やWebサイトのユーザーから取得する情報に焦点を当てています。オンライン上で収集するデータや、サービス提供時に扱う情報など、より限定的で具体的な範囲を対象とします。
ただし、プライバシーマーク(Pマーク)認定を取得する場合には必須項目となっており、PMS(個人情報保護マネジメントシステム)構築の一部として策定が求められます。
一方、プライバシーポリシーは、個人情報保護法で義務づけられた「利用目的の公表」や「取扱い方法の明示」を実現するための手段です。特に、Webサイトやアプリを運営する企業は、利用者からの個人情報取得時にこれを公表することが法的に求められます。
記載内容
個人情報保護方針は「理念的・抽象的な表現」が多く、企業としての考え方や方針を示すのに対し、プライバシーポリシーは「具体的な取り扱い方法」を細かく記載します。
例えば、個人情報保護方針では「当社は個人情報を適正に取得し、目的外利用を行いません」といった基本姿勢を述べる一方で、プライバシーポリシーでは「お問い合わせ対応のために氏名・メールアドレスを取得し、第三者提供は行いません」といった具体的な情報が明記されます。
つまり、個人情報保護方針は「理念・方針」を示す文書であり、プライバシーポリシーは「実際の運用内容」を説明する文書といえます。
最後に、個人情報保護方針とプライバシーポリシーの主な違いをわかりやすく表にまとめましたので、参考にしてください。
| 相違点 | 個人情報保護方針 | プライバシーポリシー |
|---|---|---|
| 目的 | 個人情報保護に関する企業の理念・方針を明示 | 個人情報の具体的な取扱い内容を明示 |
| 対象範囲 | 社員・顧客・取引先など、組織全体の情報 | 顧客・利用者など、外部から取得する情報 |
| 位置づけ | 経営方針・組織理念(内部統制の一部) | 法令遵守・利用者説明責任の一部 |
| 法的義務 | なし(Pマーク認定では必須) | 個人情報保護法により実質的に義務化 |
| 内容の具体性 | 抽象的・理念的 | 具体的・実務的 |
| 公開先 | 社内外 | 外部向け |

個人情報保護方針とプライバシーポリシーを設定する必要性・メリット
ここでは、個人情報保護方針とプライバシーポリシーを設定する必要性・メリットについて解説します。
個人情報保護に関する対外的な信頼獲得
最近では、情報漏えいや不正利用などのリスクが社会的問題として注目されており、消費者や取引先は「個人情報を安心して預けられる企業かどうか」を重視しています。
個人情報保護方針とプライバシーポリシーを明確に示すことで、企業が法令を遵守し、適切に情報を管理していることを周知できます。こうした取り組みにより、以下のようなメリットが期待できます。
- 顧客からの信頼性向上
- 取引先・委託先との契約上の安心感の提供
- 企業イメージやブランド価値の向上
このように、両方の方針を整備することは、「信頼を獲得するための情報公開」という側面を持っています。
個人情報保護法遵守のリスク軽減
プライバシーポリシーは、個人情報保護法に基づく利用目的の通知・公表を実現する手段であり、これを整備していない企業は法令違反となるおそれがあります。
一方、個人情報保護方針を策定しておくことで、社内における情報管理体制の方向性が定まり、従業員一人ひとりが法令遵守を意識した行動を取るようになります。
両者を整備することで、以下のようなメリットが期待できます。
- 不適切な情報管理や誤操作による漏えいリスクの低減
- 行政指導や罰則を受けるリスクの回避
- 内部統制・監査への対応強化
つまり、両者の方針を整備することで、コンプライアンス(法令遵守)体制の一部として機能するのです。
従業員の情報セキュリティ意識の向上
個人情報保護方針を社内に浸透させることで、従業員が日常業務の中で個人情報の重要性を意識し、適切な取り扱いを徹底できるようになります。
特に、定期的な研修や社内掲示、インターネット上への掲載などを通じて方針を共有することで、「情報保護は全社員の責任である」という意識を組織全体に定着させられます。
またプライバシーポリシーを外部に公開することは、従業員にとっても「自社の約束」を意識する機会となり、社内外で一貫した情報管理体制の維持に役立ちます。
個人情報保護方針とプライバシーポリシーに違反した場合のリスク
個人情報保護方針やプライバシーポリシーを定めていても、その内容に違反する取り扱いを行ってしまうと、企業は法的・社会的リスクを負うことになります。
ここでは、個人情報保護方針とプライバシーポリシーに違反した場合の3つのリスクについて解説します。
対外的な信頼・ブランドイメージの失墜
個人情報の取り扱いミスや方針に反する対応が発覚すると、企業への信頼は一気に失われます。
たとえ法的な罰則がなくても、マスコミやSNSなどによって情報が拡散すれば、「個人情報の管理がずさんな会社」という印象が定着してしまいます。
結果として、顧客離れや取引停止、採用活動への悪影響など、長期的なブランドイメージの低下を招くことになります。最悪の場合には業績が悪化して事業継続さえも難しくなる可能性もあるのです。
一度失墜した信頼・イメージの回復には多大な時間とコストがかかるため、違反を防ぐための日常的な管理が欠かせません。
損害賠償や法的罰則
プライバシーポリシーは個人情報保護法に基づく「公表義務」の一部であり、その内容に反した取り扱いを行うと、個人情報保護委員会による指導や勧告、命令の対象となります。
さらに命令に違反した場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金といった刑事罰が科されることもあります。
また個人情報漏えいによって顧客やユーザーなどに損害を与えた場合は、損害賠償請求が発生する可能性もあります。法的制裁だけでなく、訴訟対応や再発防止策のコストも発生するため、企業経営に大きな影響を及ぼすリスクとなります。
Pマークなどの取り消し
Pマークなどの認証を取得している企業の場合、個人情報保護方針やプライバシーポリシーの違反は認証基準の不適合とみなされることがあります。
重大な違反や再発が確認された場合、認証の停止や取り消しとなるケースもあり、企業の信頼性を大きく損ないます。特に取引先からの信用が求められるBtoB企業では、Pマークの取り消しによって新規契約や入札機会の減少につながることもあります。

個人情報保護方針とプライバシーポリシーのどちらを作成すべき?

「個人情報保護方針」と「プライバシーポリシー」は、どちらも個人情報を適切に扱うために欠かせない文書です。しかし、目的や対象が異なるため、どちらを先に作成すべきか迷う場合があります。
結論としては、原則として両方を作成することが望ましいです。
個人情報保護方針は企業全体としての理念や基本方針を示すものであり、プライバシーポリシーは実際に顧客や利用者から取得する情報の取扱いを具体的に説明するものです。
このように両者は役割が異なるため、両方を整備することで、社内外への説明責任と運用の透明性を両立できます。
ただし、「どちらも同時に整備するのは難しい」という企業もあるでしょう。その場合に、企業の集客方法や事業形態ごとにおすすめの作成順番について、以下の表にまとめました。
| 集客・事業形態 | 優先して作成すべき文書 | 理由 |
|---|---|---|
| WebサイトやECサイトなどのオンライン上で個人情報を取得する企業 | プライバシーポリシー | ユーザーから個人情報を取得する際、利用目的や管理体制を明示する必要があるため。 |
| 社内で人事・顧客情報などを管理しているBtoBのオフライン事業 | 個人情報保護方針 | 社内全体の情報管理体制を明確にし、従業員教育や統制を徹底する必要があるため。 |
| 官公庁・大企業との取引が多い企業 | 個人情報保護方針 | 企業としての基本方針を示し、その後に具体的な運用内容を整備する順序がおすすめ。 |
| 個人事業主・フリーランスなど、Webでサービス提供する個人 | プライバシーポリシー | 顧客に個人情報の利用目的を明示する必要があるため。 |
個人情報保護方針とプライバシーポリシー設定のポイント
ここでは、個人情報保護方針とプライバシーポリシー設定時に意識すべき3つのポイントについて解説します。
わかりやすい表現を使用する
文章は、利用者や従業員に誰でも理解できる表現を用いることが基本です。法律用語や専門用語ばかりを並べると、内容が理解されず、せっかくの方針やポリシーの意味が伝わらなくなります。
具体的には、以下のような工夫を検討しましょう。
- 専門用語は可能な限りわかりやすい言葉に置き換える
- 箇条書きや表を使い、項目ごとに整理する
- 利用者にとって想定される状況例を簡単に記載する
例えば、「個人情報を適正かつ厳格に管理し、漏えい防止のための物理的・技術的及び組織的安全管理措置を講ずる」と記載されていると、イメージしにくいですよね。「氏名やメールアドレスなどの個人情報は、社内でアクセス権限を制限して管理します」のように置き換えると、誰が見ても取り組み内容を理解しやすくなります。
全体的な方針から具体的な内容まで、バランスを意識する
個人情報保護方針とプライバシーポリシーを作成する際には、方針と具体性のバランスが重要です。理念だけでは実務が不明確になり、具体的な運用内容だけでは企業としての姿勢が伝わりにくくなるでしょう。
例えば、以下のように全体を網羅しつつ具体的な内容を取り入れるように工夫することが大切です。
- 個人情報保護方針では、「当社は個人情報を適切に取り扱い、利用者の信頼を守ります」と基本姿勢を示す
- プライバシーポリシーでは、「お問い合わせフォームで取得した氏名とメールアドレスは、お問い合わせ対応のみに使用し、第三者提供は行いません」と具体的な運用を記載する
このように両方を組み合わせることで、内部統制と外部説明責任の両立が可能になります。
定期的に更新する
個人情報保護方針やプライバシーポリシーは、作成したら終わりではありません。
法律改正や社内体制の変更、新しいサービスの提供などに合わせて定期的に見直し・更新することが不可欠です。
また、更新時には社内教育や外部への周知も同時に行うことで、全社的に一貫した情報管理体制を維持できます。
更新が遅れると、内容が現状に合わず、法令違反や誤解を招くリスクがあります。個人情報保護方針やプライバシーポリシーが形式だけのものにならないよう、継続的な運用を心がけましょう。
具体的には、以下のようなタイミングでの見直しや更新が考えられます。
- 年1回の見直しと改訂
- 新しいサービスの開始時
- 法規制の発行・改訂時
- 社会的に重大な問題やインシデント発生時
見直しのタイミングを定めておくことで、常に最新の情報を反映させられます。顧客や取引先、従業員などすべてのステークホルダーに安心してもらえるような運用を目指しましょう。

まとめ
この記事では、プライバシーポリシーと個人情報保護方針の違いについて、解説しました。
プライバシーポリシーは具体的な情報の取扱いを示す文書、個人情報保護方針は企業の理念や基本方針を示す文書です。両者は似ているものの、目的や内容が異なり、どちらも作成することがおすすめです。
法令遵守と利用者からの信頼を得られるような内容を盛り込むためには、コンサルタントに依頼することも検討しましょう。

ISOプロでは月額4万円から御社に合わせたISO運用を実施中
ISOプロではISO各種の認証取得から運用まで幅広くサポートしております。
また、マニュアル作成など御社に合わせたムダのない運用を心がけており、既に認証を取得しているお客様においてもご提案しております。
サポート料金においても新プランを用意し、業界最安級の月額4万円からご利用いただけます。
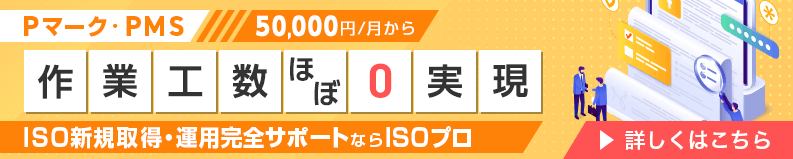




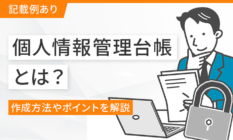





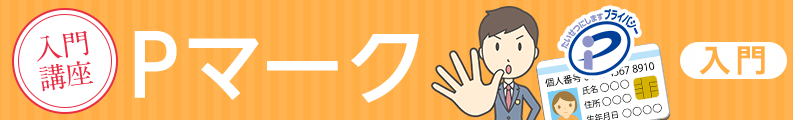






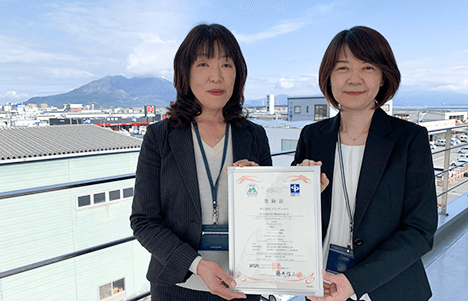




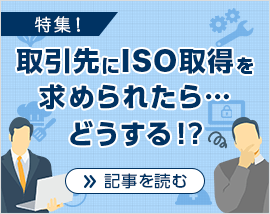













こんな方に読んでほしい