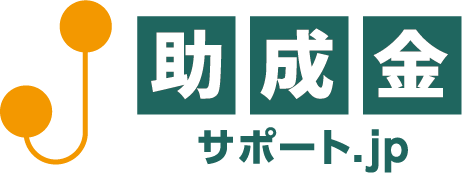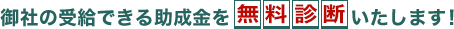少子高齢化が進む日本では、企業の人手不足が深刻さを増していることから、高齢者雇用が労働力確保の重要な要素となりつつあります。
こうした現状において、厚生労働省は「高年齢労働者処遇改善促進助成金」を制定し、企業の60~64歳の処遇改善(賃金規定等の増額改定)を支援してきました。しかし、この制度は令和7年(2025年)3月31日をもって廃止されました。
この記事では高年齢労働者処遇改善促進助成金の支給要件や助成額、廃止後に活用できる代替助成金について解説します。
高年齢労働者処遇改善促進助成金とは
高年齢労働者処遇改善促進助成金とは、「60~64歳までの高年齢労働者の処遇改善に向けて、高年齢労働者に適用される賃金規定の増額改定などに取り組む事業主を助成する制度」です。※令和7年度(2025年度)3月31日をもって廃止
少子高齢化が進む中、高齢者の就業機会を確保しつつ、企業にとっても人材不足を補える仕組みとして活用されてきました。
支給要件
高年齢労働者処遇改善促進助成金の主な支給要件をまとめました。
- 就業規則などにおいて賃金規定を改定し、すべての対象労働者の1時間あたりの賃金を、60歳時点の75%以上に増額する措置を講じている事業主であること
- 賃金規定の改定により対象労働者の毎月の賃金を増額した結果、改定前6か月間と比べ、改定後6か月間の高年齢雇用継続基本給付金の総額が減少している事業主であること
- 支給申請日において改定後の賃金規定等を継続して運用している事業主であること
助成額
高年齢労働者処遇改善促進助成金の助成額は、以下の計算式で計算します。
(改定前の高年齢雇用継続基本給付金の総額-改定後の高年齢雇用継続基本給付金の総額)×2/3(中小企業事業主以外は1/2)
同一の支給対象事業主に対する支給申請回数は、支給対象期の第1期~第4期までの最大4回(2年間)までとなっています。
申請の流れ
高年齢労働者処遇改善促進助成金の基本的な申請の流れを解説します。
- 賃金規定等改定計画書を作成し、添付書類とともに管轄の労働局に提出する
- 書類をもとに、支給認定の審査が行われる
- 認定された場合、事業を実施する
- 改定後、6か月以上継続して運用する
- 事業実施後、一定期間内に必要書類を準備して支給申請を行う
- 問題がなければ、支給が決定する
- 助成金が振り込まれる
具体的な手続きは、最寄りの労働局・ハローワークに問い合わせる必要があります。


高年齢労働者処遇改善促進助成金の代わりに活用できる助成金

冒頭でも解説しましたが、令和7年3月31日をもって高年齢労働者処遇改善促進助成金は廃止されました。
ここでは、高年齢労働者処遇改善促進助成金の代わりに、高年齢労働者の雇用に活用できる助成金について解説します。
エイジフレンドリー補助金
エイジフレンドリー補助金とは、「高年齢労働者が安全に仕事に取り組めるように、労働災害防止対策や労働者の健康保持増進のための取り組みを支援する制度」です。
取り組み内容に応じて、以下の4つのコースが設置されています。
・総合対策コース
労働安全衛生の専門家によるリスクアセスメントと、それに基づく設備改善・工事費用を支援するコース
・職場環境改善コース
高年齢労働者の身体機能低下を補う設備や熱中症対策設備の導入を支援するコース
・転倒防止・腰痛予防のための運動指導コース
専門家による身体機能チェックと、転倒や腰痛予防のための運動指導を支援するコース
・コラボヘルスコース
健康スコアリングや事業所カルテなどを活用した健康増進・生活習慣改善施策を支援するコース
過去には、「高年齢労働者が作業中に転倒しないように、段差部分にスロープを設けたい」「熱中症予防のために空調服を導入したい」といった働きやすい環境づくりに役立つ設備・機器の導入が対象となっています。
エイジフレンドリー補助金の詳細は、以下の記事をご覧ください。
関連記事:【令和7年度最新】エイジフレンドリー補助金とは?要件や助成額を解説
65歳超雇用推進助成金
65歳超雇用推進助成金とは、65歳以上への定年引上げ等・高年齢者の雇用管理整備・無期雇用転換の3コースからなる制度です。
取り組み内容に応じて、以下の3つのコースが設置されています。
- 65歳超継続雇用促進コース
65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかを実施した事業主に対して助成するコース - 2高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者向けの雇用管理制度の整備などにかかる措置を実施した事業主に対して助成するコース - 3高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を、無期雇用労働者に転換させた事業に対して助成するコース
例えば、65歳以上への定年の引上げや定年の廃止、高年齢労働者の賃金・人事処遇制度の導入や改善などを行った場合に対象となります。
65歳超雇用推進助成金の詳細は、以下の記事をご覧ください。
関連記事:【令和6年度】65歳超雇用推進助成金とは?各コースを徹底解説
人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)
人材確保等支援助成金は、人材の確保・定着を目的とし、企業の設備・機器の導入や体制づくりに関する取り組みを支援する制度です。
そのうち、雇用管理制度助成コースは、雇用管理制度または業務の負担軽減に関する機器などの導入による雇用管理改善を行い、離職率の低下に取り組んだ事業主を助成するコースです。
なお、これまで新たな整備計画の受付が停止されていたもの、令和7年4月1日より受付が再開されています。
例えば、以下のような「雇用管理制度」「業務の負担軽減に関する機器」の導入が助成対象となります。
- 雇用管理制度:賃金規定制度、諸手当等制度、人事評価制度、職場活性化制度、健康づくり制度
- 業務の負担軽減に関する機器:従業員の直接的な作業負担を軽減する機器・設備
人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)の詳細は、以下の記事をご覧ください。
関連記事:【2024最新】人材確保等支援助成金とは?各コースを徹底解説
「そもそも助成金って何?」「個人事業主でももらえるものなの?」という疑問をお持ちの方はこちら!助成金の制度や仕組みについてわかりやすく解説しています!
助成金とは?対象者や受給条件・申請の方法まで徹底解説高年齢労働者処遇改善促進助成金の代替となる支援制度の検索方法

ここでは、高年齢労働者処遇改善促進助成金の代替となる支援制度の検索方法について解説します。
ホームページを検索する
最も基本的な方法は、国や自治体の公式ホームページを活用することです。特に以下のWebサイトは、高年齢労働者の雇用や職場環境改善に関する最新情報の入手に有効です。
- 厚生労働省:「助成金のご案内」ページでは、高年齢者雇用関連の助成金制度を確認できる
- 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED):高齢者雇用に関する支援策や事例を掲載している
- 都道府県労働局や自治体サイト:地域独自の助成金や補助制度が案内されている場合がある
検索時は、「高年齢者 雇用 助成金」「65歳 雇用継続 支援」などの具体的なキーワードを組み合わせると、希望に合った助成金制度を見つけやすくなります。
助成金コンサルタントに相談する
助成金は年度ごとに内容が変わることが多いため、自社の状況に合う制度を正確に把握するのは、難しいといえます。
助成金に精通した人材がいない場合には、コンサルタントに申請サポートを依頼することで、以下のようなメリットが得られます。
- 最新情報に基づき、自社に最適な制度の提案を受けられる
- 申請に必要な書類や手順を具体的に案内してもらえる
- 申請ミスを防止し、申請にかかる手間・時間を大幅に削減できる
助成金コンサルタントの詳細は、以下の記事をご覧ください。
関連性:助成金・補助金はコンサルに依頼すべき?費用相場や選び方を解説


まとめ
この記事では、この記事では高年齢労働者処遇改善促進助成金の支給要件や助成額、廃止後に活用できる代替助成金についても解説しました。
高年齢労働者処遇改善促進助成金は、令和7年3月31日に廃止されました。
高年齢労働者向けの助成金制度は複数あるため、高年齢労働者処遇改善促進助成金の代替となる助成金を活用したいと考えている企業の方は、プロの助成金コンサルタントへの依頼がおすすめです。
自社の希望や現状に適した助成金制度の提案から申請サポートまで、包括的なサポートが受けられます。確実な受給を目指すためにも、まず以下から無料相談を試してみてはいかがでしょうか。
無料相談はこちら