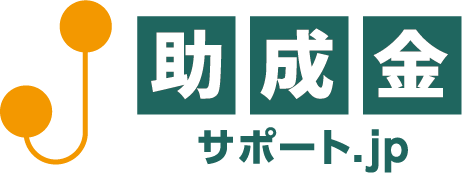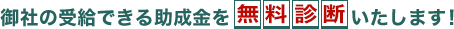2024年10月から地域別最低賃金が50円以上賃上げされたことや、人材不足への対応として賃上げの動きが各企業で活発化しています。
しかし、すべての企業が積極的に賃上げできるわけではありません。特に中小企業では賃上げによる人件費の増加は経営難につながる可能性があります。そこで活用したい制度に賃上げ促進税制や助成金制度が挙げられます。
この記事では賃上げ促進税制の概要や導入メリット、注意点、賃上げに活用できる助成金について解説します。
賃上げ促進税制とは
賃上げ促進税制とは、「前年度よりも雇用者の給与を引き上げた場合に、増加額の一部を法人税(個人事業主の場合は所得税)から税額控除できる制度」です。
賃上げ促進税制が注目されている背景には、近年の急激な物価上昇や人材不足に対応するために、賃上げを表明する企業が増えたことが挙げられます。しかし、すべての企業が賃上げに対応できているわけではなく、原資の確保が難しい企業も多くあります。
そうした苦境であっても賃上げを実施できるように、中小企業や個人事業主も活用できる優遇措置として、賃上げ促進税制が注目されているのです。
また令和6年度税制改正において、賃上げ促進税制が3年間の延長・拡充されたことで、これまでよりも適用する効果が高まっています。
賃上げ促進税制の3つの区分
賃上げ促進税制は、企業の規模によって以下の3つの区分が設けられています。
| 全企業向け賃上げ促進税制 | 青色申告書を提出する全企業または個人事業主 |
|---|---|
| 中堅企業向け賃上げ促進税制 | 青色申告書を提出する従業員数2,000人以下の法人または個人事業主 |
| 中小企業向け賃上げ促進税制 | 青色申告書を提出する資本金1億円以下の中小企業者など、または従業員数1,000人以下の個人事業主 |
この3つの区分は、令和6年4月1日~令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度で適用されます。(個人事業主は、令和7年~令和9年までの各年が対象)


賃上げ促進税制の適用要件・税額控除率
ここでは、3つの区分それぞれにおける賃上げ促進税制の適用要件について解説します。
必須要件
必須要件では、事業規模に応じて労働者の給与などの支給額を賃上げすることが必要です。以下に、必須要件となる給与等支給額の増加率と、それぞれに対応した税額控除率をまとめました。
| 事業規模 | 給与等支給額の増加率 (前事業年度比) |
税額控除率 |
|---|---|---|
| 全企業向け | 3%以上増 | 10% |
| 4%以上増 | 15% | |
| 5%以上増(新設) | 20% | |
| 7%以上増(新設) | 25% | |
| 中堅企業向け | 3%以上増 | 10% |
| 4%以上増 | 25% | |
| 中小企業向け | 1.5%以上増 | 15% |
| 2.5%以上増 | 30% |
上乗せ要件①:教育訓練費
必須要件に追加して教育訓練費を、さらに税額控除率として上乗せできます。
ここでいう教育訓練費とは、「国内雇用者の職務に必要な技術・知識の習得もしくは向上させるために支出する費用のうち一定のもの」です。
具体的には、以下のような費用が教育訓練費として申請できます。
- 法人が教育訓練を自ら行う場合の費用(外部講師謝金等、外部施設使用料など)
- 第三者に委託して教育訓練を行わせる場合の費用(研修委託費等)
- 第三者が行う教育訓練に参加させる場合の費用(外部研修参加費等)
上乗せ要件を満たすと、以下の税額控除率が上乗せされます。
| 全企業向け | 前年度比+10% →税額控除率を5%上乗せ |
|---|---|
| 中堅企業向け | |
| 中小企業向け |
参照:中小企業庁|「賃上げ促進税制」パンフレット(令和6年3月時点版)
ただし、教育訓練費の上乗せ要件は、「適用事業年度の教育訓練費の金額」が「適用事業年度の全雇用者に対する給与等支給額」の0.05%以上である場合に限り適用可能であるため、注意が必要です。
上乗せ要件②:くるみん認定
子育てとの両立や女性の活躍支援のための環境整備を推進する企業において、さらに税額控除率を上乗せできます。
この要件を満たすためには、「くるみん」認定や「えるぼし」認定などを取得することが必要です。具体的な要件と税額控除率を以下にまとめました。
| 事業規模 | 上乗せ要件 | 税制控除率 |
|---|---|---|
| 全企業向け | 以下のいずれかを取得
|
5%上乗せ |
| 中堅企業向け | 以下のいずれかを取得
|
|
| 中小企業向け | 以下のいずれかを取得
|
参照:中小企業庁|「賃上げ促進税制」パンフレット(令和6年3月時点版)
「そもそも助成金って何?」「個人事業主でももらえるものなの?」という疑問をお持ちの方はこちら!助成金の制度や仕組みについてわかりやすく解説しています!
助成金とは?対象者や受給条件・申請の方法まで徹底解説賃上げ促進税制を活用するメリット

賃上げ促進税制を活用するメリットを解説します。
高い節税効果を得られる
賃上げ促進税制は、事業主が負担している法人税額や所得税額から税額控除できるため、高い節税効果を得られることになります。
さらに中小企業の場合には、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった場合にも、5年間の繰越しが可能です。そのため継続的な節税につながります。
人材育成に活用できる
賃上げ促進税制の上乗せ要件の一つに、教育訓練費が挙げられます。従業員の賃上げには負担がかかるものの、人材育成をすることで税額の負担を低減できます。
少子高齢化により人材不足が深刻になっている日本企業において、人材の育成は急務です。そのため節税をしながら教育訓練に活用できる本制度の大きなメリットといえるでしょう。
従業員の職場満足度向上につながる
賃上げ促進税制を活用することは、従業員の給料やボーナスの増額につながるため、従業員の職場満足度の向上につながります。
また給料やボーナスが高く、安定している企業は求職者にとっても魅力的に映るでしょう。そのため、優れた人材の獲得にも役立ちます。


従業員の賃上げに活用できる助成金一覧

ここまで賃上げ促進税制について解説しましたが、実は助成金制度の中にも従業員の賃上げに活用できる助成金が存在します。
助成金とは、「事業主の取り組みを支援するために、国や地方自治体が助成するお金」のことです。助成金ごとに定められた要件を満たすことで受給でき、原則返済は不要です。そのため、多くの企業が自社の課題解決に助成金を活用しています。
関連記事:助成金とは?注意点など知っておきたい基礎知識をわかりやすく解説!
ここでは賃上げすることにより活用できる助成金を解説します。
キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
キャリアアップ助成金とは、パート・アルバイトや派遣社員などの非正規雇用労働者の「正社員化」「処遇改善」に取り組んだ事業主を助成する制度です。
6つのコースがありますが、賃金の引き上げに活用できるのは、「賃金規定等改定コース」です。非正規雇用労働者の基本給などの賃金規定を3%増額改正し、実際に6か月以上適用した企業に、以下の助成額が受給されます。
| 企業規模 | 賃金引き上げ率 3%以上~5%未満 |
賃金引き上げ率 5%以上 |
|---|---|---|
| 中小企業 | 5万円 | 6万5,000円 |
| 大企業 | 3万3,000円 | 4万3,000円 |
キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の詳細は、以下の記事をご覧ください。
関連記事:【2024最新】キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)を解説
業務改善助成金
業務改善助成金とは、「生産性向上のための設備投資などの取り組み」と「事業場内最低賃金の30円以上の引き上げ」の両方を行った事業主を助成する制度です。
助成率は、申請を行う事業場の引き上げ前の事業場内最低賃金によって、以下のように異なります。
| 870円未満 | 9/10 |
|---|---|
| 870円以上920円未満 | 4/5(9/10) |
| 920円以上 | 3/4(4/5) |
※助成上限額あり
業務改善助成金の主な支給要件は、以下の3つを満たすことです。
- 中小企業・小規模事業者
- 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
- 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由に当てはまっていないこと
POSレジシステムやテイクアウト注文用の予約サイトの開設など、幅広い取り組みに活用できるうえ、事業場内最低賃金の引き上げにかかる負担を軽減できます。
業務改善助成金の詳細は、以下の記事をご覧ください。
関連記事:【2024年最新】業務改善助成金とは?概要や目的、助成額を徹底解説
まとめ
この記事では、賃上げ促進税制の概要や導入メリット、注意点、賃上げに活用できる助成金について解説しました。
賃上げ促進税制を適用することで、高い節税効果や従業員の職場満足度向上が期待できます。適用要件を確認したうえで賃上げに取り組みましょう。
また賃上げによって返済不要の資金調達が可能な助成金制度を活用できる可能性があります。
そのため、賃上げのための資金不足にお悩みの場合には、まずプロの助成金コンサルタントに相談することがおすすめです。以下から無料相談を試してみてはいかがでしょうか。
【無料】賃上げに使える助成金の相談をする