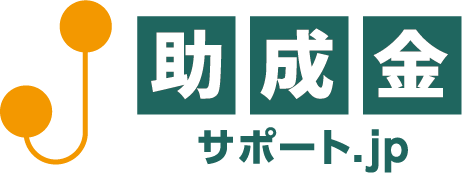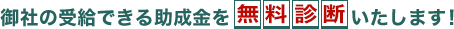人手不足や業務効率化に取り組みたい企業を支援する「働き方改革推進支援助成金」では、車両の導入は対象となるのでしょうか。
移動や輸送の効率化につながる車両の導入は、労働時間の短縮や安全性向上につながる施策として、多くの企業が検討しています。
しかし、「助成金で車両は本当に対象になるのか?」「対象外となるケースは?」といった疑問を持つ方も少なくありません。
そこで、この記事では「働き方改革推進支援助成金」の概要や車両の購入が対象となるケース・対象外となるケースを解説したのち、活用事例をわかりやすく紹介します。
働き方改革推進支援助成金とは
働き方改革推進支援助成金とは、「生産性を高めながら、働き方改革に向けた取り組みを行う中小企業事業主・小規模事業主を対象に、その実施にかかる費用の一部を助成する制度」です。
取り組み内容に応じて、以下の4つのコースが設置されています。
・業種別課題対応コース
生産性を向上させ、時間外労働の削減や週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入や医師の働き方改革推進に向けた環境整備に取り組む、建設業・運送業などの特定の業種に該当する中小企業事業主を支援するコース
・労働時間短縮・年休促進支援コース
生産性を向上させ、時間外労働の削減や年次有給休暇・特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援するコース
・勤務間インターバル導入コース
勤務間インターバル制度の導入に取り組む中小企業事業主を支援するコース
・団体推進コース
中小企業事業主の団体やその連合団体が、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主の労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引き上げに向けた取組を実施した場合に、その事業主団体等に対して支援するコース
働き方改革推進支援助成金の各コースの支給要件や助成額などの詳細は、以下の記事をご覧ください。
関連記事:【2025年拡充予定】働き方改革推進支援助成金とは?各コースを徹底解説


働き方改革推進支援助成金では車両購入は対象?

働き方改革推進支援助成金は、中小企業が労働環境を改善するための取り組みを支援する制度です。設備投資や業務効率化を目的とした経費が助成対象になりますが、「車両購入」が対象となるかは条件をよく確認する必要があります。
結論として、業務用として使用する貨物自動車などに限って助成対象とされており、乗用車は原則として対象外です。
ここでは、働き方改革推進支援助成金で対象となる車両の条件や対象外となる車両例について解説します。
対象となる車両の条件
働き方改革推進支援助成金において、車両購入が対象となる車両の条件には、「車検証の用途欄」と「生産性向上に寄与するか」の2つが挙げられます。
車検証の用途のうち、支給対象となる車両は、「貨物自動車・特種用途自動車」の2つです。以下に、貨物自動車・特種用途自動車に該当する車種についてまとめました。
| 貨物自動車 | 特種用途自動車 | 「乗用」でも支給対象となる例外 |
|---|---|---|
|
|
車いす移動車(福祉車両) |
対象外となる車両の例
働き方改革推進支援助成金では、以下の車両は通常事業活動に伴う経費と見なされ、対象外となります。
- 電動アシスト折り畳み自転車
- 原動機付き自転車
- 超小型EV(電気自動車)
参考:働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)「R7働き方改革推進支援助成金Q&A(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、勤務間インターバル導入コース共通)」
「そもそも助成金って何?」「個人事業主でももらえるものなの?」という疑問をお持ちの方はこちら!助成金の制度や仕組みについてわかりやすく解説しています!
助成金とは?対象者や受給条件・申請の方法まで徹底解説働き方改革推進支援助成金で車両を購入する際の注意点
ここでは、働き方改革推進支援助成金で車両を購入する際の注意点について解説します。
新規雇用時の車両購入は対象外
対象となる貨物自動車・特種用途自動車の導入であっても、新規に労働者を雇用する際の車両購入は対象外です。
厚生労働省によると、新たな人材を追加するのに合わせて、車両を追加導入することにより受注数の増加を狙う場合は、既存労働者の作業時間の短縮につながらないため、労働能率の向上に向けた取り組みとは認められないと、見解を発表しています。
車両本体以外の関連費用の中には対象外となる費用がある
自動車の購入においては、車両本体価格以外の関連費用の中には、対象となるもの・対象外となるものがあります。以下に、それぞれの費用についてまとめました。
| 対象となる関連費用 |
|
|---|---|
| 対象外となる関連費用 |
|
また、希望ナンバー交付手数料の他、オーディオなどのオプション装備についても原則として対象外です。
一方、クレーン、リフトなどの労働能率の増進につながる機器や、カーペットマット、サイドバイザー(ドアバイザー)などの車両に通常装備されるものは、助成対象となります。
カーナビなどのオプションは、対象となる可能性がある
自動車を購入する場合に併せて購入したいカーナビやバックモニターなどのオプションは、対象となる可能性があります。これらオプションが対象となるかどうかの基準は、「導入により、さらなる労働能率の増進につながる」と判断された場合です。
ただし、すべてのオプションが対象となるわけではなく、業務上の必要性や導入効果を資料などで明確に示す必要があるため、申請前に助成金コンサルタントや労働局に確認することをおすすめします。


働き方改革推進支援助成金を車両購入に活用した事例

ここでは、働き方改革推進支援助成金を車両購入に活用した事例を紹介します。
【運送業】10トン貨物車の導入
香川県で運送業を営む会社では、働き方改革推進支援助成金を活用して積載量10トンの貨物自動車を1台導入しました。
以下に、この会社における車両導入に至る経緯や取り組みの成果をまとめました。
| 背景 | 従来運用していた貨物自動車の積載量は4トンであり、一度に積載できる荷物の量が限られていた。そのため、1件の依頼であっても荷物が多い場合は、複数の車両に分けて運搬する必要があり、負担を感じていた。 |
|---|---|
| 成果 | 貨物自動車の積載量が4トンから10トンになり、1台で約2.5倍の荷物を運搬できるようになったことで、以下のような成果が得られた。
|
今回の取り組みによって労働時間を削減し、令和6年4月から施行された改善基準告示に対応できました。業務効率化を継続しながら、今後は賃金の引き上げにも注力したいと検討されています。
参考:働き方改革推進支援助成金「生産性向上のヒント集」(2024年3月作成)
【道路貨物運送業】新型トレーラーの導入
石川県で道路貨物運送業を営む会社では、働き方改革推進支援助成金を活用して新型トレーラーを1台導入しました。
以下に、この会社における車両導入に至る経緯や取り組みの成果をまとめました。
| 背景 | 慢性的な人員不足により従業員への負担が増え、受注量を制限せざるを得ない状況だった。 |
|---|---|
| 成果 | 従来のトレーラーよりも積載量が多い新型トレーラーを導入したことで、以下のような成果が得られた。
|
本制度の活用により、運搬業務が大幅に効率化されました。また就業規則を改定し、ボランティア休暇を導入したことで、従業員の負担軽減にも取り組んでいます。
参考:働き方改革推進支援助成金「生産性向上のヒント集」(2023年3月作成)
【職別工事業】フォークリフトの導入
広島県で職別工事業を営む会社では、働き方改革推進支援助成金を活用してフォークリフトを1台導入しました。
以下に、この会社における車両導入に至る経緯や取り組みの成果をまとめました。
| 背景 | 総重量が2トン程度ある足場資材や塗装缶の積み下ろしを手作業で行っており、負担が大きいうえに時間もかかっていた。 |
|---|---|
| 成果 | フォークリフトを導入したことで、以下のような成果が得られた。
|
本制度の活用により、足場資材や塗装缶の積み下ろし作業が大幅に効率化されました。また就業規則を改定し、11時間以上の勤務間インターバルを新たに導入したことで、従業員の負担軽減にも取り組んでいます。
参考:働き方改革推進支援助成金「生産性向上のヒント集」(2023年3月作成)
まとめ
この記事では、働き方改革推進支援助成金の概要や車両の購入が対象となるケース・対象外となるケース、実際の導入事例を解説しました。
働き方改革推進支援助成金では、業務効率化や労働環境の改善につながる場合では、車両購入も対象となる可能性があります。要件を正確に満たすためには、申請前に制度内容を十分に確認することが欠かせません。
そこで、働き方改革推進支援助成金の受給を検討している事業主の方は、プロのコンサルタントへの依頼がおすすめです。確実な受給を目指すためにも、まず以下から無料相談を試してみてはいかがでしょうか。
無料相談はこちら