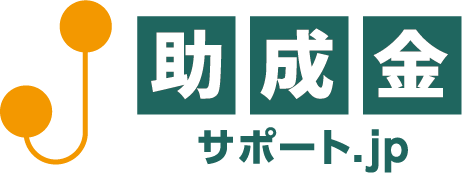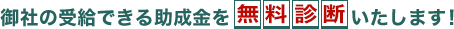「働き方改革関連法」により、企業はこれまでの労働環境を改善し、時間外労働や働き方の実現に向けた取り組みを行うことが義務付けられました。この対応をサポートするために策定されたのが、「働き方改革推進支援助成金」です。必要性を理解しつつも、資金的に対応することが難しいと感じている企業の方は、必見の助成金といえるでしょう。
この記事では、中小企業の働き方改革の実施状況や、「働き方改革推進支援助成金」の基本的な内容、申請方法について解説します。
働き方改革とは
厚生労働省によると働き方改革とは、「働く人々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で選択できるようにするための改革」です。
これまでは、「少子高齢化に伴う人材不足」「働く人々のニーズの多様化」などの課題に対応するためには、生産性向上や就業機会の拡大、意欲・能力を存分に発揮できる環境をつくることが不可欠でした。
しかし、これからは事情に応じた多様な働き方を選択できるような働き方改革を行うことで、働きやすい社会を実現することが求められています。
働き方改革の必要性
特に日本国内雇用の約7割を担う中小企業・小規模事業者において、働き方改革の必要性が増しています。
その理由には、魅力ある職場づくりの一環として働き方改革を実施することで、人手不足の解消につながることが挙げられるでしょう。
さらには、働き方改革を行うことで「魅力ある職場づくり」→「人材の確保」→「業績の向上」→「利益増」の好循環をつくる足がかりにするために、働き方改革を行うことが重要なのです。
参照:厚生労働省「働き方改革広がる!|働き方改革のポイントをチェック」


働き方改革推進支援助成金とは

働き方改革を進めるうえで確認しておきたい助成金の一つに、働き方改革推進支援助成金があります。
「働き方改革推進支援助成金」とは、働き方改革に取り組む中小企業の事業主を対象にしている助成金です。職場環境の整備に必要な費用の一部に対して資金が援助されます。
実施内容により、以下の4つのコースが設定されています。
- 業種別課題対応コース
- 労働時間短縮・年休促進支援コース
- 勤務間インターバル導入コース
- 団体推進コース
それぞれのコースについて詳しく解説します。この情報は2025年3月12日現在のものであるため、申請を検討されている方は、厚生労働省のホームページから最新情報を確認してください。
2025年4月から拡充予定!
令和7年度予算案において、生産性向上や正規・非正規の格差是正、より高い処遇への労働移動などを促進し、労働市場全体の賃上げを支援するための施策として「賃上げ支援助成金パッケージ」が発表されました。
この決定により、働き方改革推進支援助成金には92億円が計上され、以下のような拡充が予定されています。
- 対象労働者の現行の賃金額を3%、5%増加させた場合の加算に加え、7%の場合の助成強化
- 恒常的な長時間労働が認められる企業における設備投資について、一部助成対象の要件を緩和
まだ詳細な拡充内容は決まっていないため、申請を検討している企業の方は最新情報を確認しましょう。
参照:厚生労働省「【参考】令和7年度予算案における「賃上げ」支援助成金パッケージ」
ここからは、令和6年度における働き方改革推進支援助成金の各コースについて解説します。
「そもそも助成金って何?」「個人事業主でももらえるものなの?」という疑問をお持ちの方はこちら!助成金の制度や仕組みについてわかりやすく解説しています!
助成金とは?対象者や受給条件・申請の方法まで徹底解説働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは

働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、「生産性を向上させつつ、時間外労働の削減、週休2日制の推進などの働き方改革推進に向けた環境整備に取り組む中小事業主を支援する制度」です。
このコースは、2024年4月1日から時間外労働の上限規制が適用された業種(建設業、運送業、病院など、砂糖製造業)のみが活用できます。
対象となる事業主
支給対象となる事業主の要件をまとめました。
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること。
- 交付申請時点で、「成果目標」1から4の設定に向けた条件を満たしていること。
- すべての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則などを整備していること。
- 常時使用する労働者数が300人以下もしくは資本金(または出資額)が3億円以下の建設業、運送業、病院など、砂糖製造業のいずれかの中小事業主であること。
支給要件
以下のうち、いずれか1つ以上を実施することで支給対象となります。
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 人材確保に向けた取り組み
- 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 労務管理用機器の導入・更新
- デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
成果目標
支給対象となる取り組みは、以下の「成果目標」1から6のうち1つ以上選択し、その達成を目指して実施してください。業種等ごとに選択できる目標が異なります。
- すべての対象事業場において、令和6年度又は令和7年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届出を行うこと
- すべての対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること
- すべての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること
- すべての対象事業場において、9時間以上の勤務間インターバル制度の規定を新たに導入すること
- すべての対象事業場において、4週5休から4週8休以上の範囲で所定休日を増加させること(建設業が選択可能)
- 医師の働き方改革推進に関する取り組みとして以下の2つをすべて実施すること(病院などが選択可能)
(1)労務管理体制の構築等
- 労務管理責任者を設置し、責任の所在とその役割を明確にすること
- 医師の副業・兼業先との労働時間の通算や医師の休息時間確保、長時間労働の医師に対する面接指導の実施 に係る協力体制の整備を行うこと(副業・兼業を行う医師がいる場合に限る)
- 管理者層に対し、人事・労務管理のマネジメント研修を実施するなど、労働時間管理について理解を深める取り組みを行うこと
(2)医師の労働時間の実態把握と管理
- 労働時間と労働時間でない時間の区別などを明確にした上で、医師の労働時間の実態把握を行うこと
助成金額・助成率
取り組みの実施にかかった経費の一部が、成果目標の達成状況に応じて支給されます。支給額は、以下のいずれか低い方の金額です。
- 成果目標1から6の上限額および賃金加算額の合計額
- 対象経費の合計額×補助率3/4
※常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取り組みで6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
ただし、いずれの場合も上限額が設定されています。成果目標によって上限額が異なるため、詳細は助成金コンサルに確認もしくは厚生労働省のホームページを確認しましょう。
参考:厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)」


働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)とは

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)とは、「生産性を向上させつつ、時間外労働の削減や年次有給休暇・特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業の事業主を支援するコース」です。
2020年4月1日から、中小企業に時間外労働の上限規制が適用されたことを受けて策定された制度です。
対象となる事業主
以下のすべてに当てはまる中小事業主が支給対象となります。
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること。
- 交付申請時点で、「成果目標」1から3の設定に向けた条件を満たしていること。
- すべての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
支給要件
以下のうち、いずれか1つ以上を実施することで支給対象となります。
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 人材確保に向けた取り組み
- 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 労務管理用機器の導入・更新
- デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
成果目標の設定
取り組みを行ううち、以下の成果目標から1つ以上を選択し、その達成を目指して実施することが必要です。
- すべての対象事業場において、令和5年度又は令和6年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこと
- すべての対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること
- すべての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること
また、上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。
助成金額・助成率
取り組みの実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて、以下のいずれかのうち低い方の金額が支給されます。
- 成果目標1から3の上限額および賃金加算額の合計額
- 対象経費の合計額×補助率3/4
※常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取り組みで6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
ただし、上限額が設けられています。成果目標によって上限額が異なるため、詳細は助成金コンサルに確認もしくは厚生労働省のホームページを確認しましょう。
参考:厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」
働き方改革推進支援助成金 (勤務間インターバル導入コース)とは

働き方改革推進支援助成金 (勤務間インターバル導入コース)とは、「勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けるために、勤務間インターバル制度の導入に取り組む中小企業の事業主を支援するコース」です。
その目的は、労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図ることにあります。
このコースは、2019年4月から制度導入が努力義務化されたことを受けて制定されました。
対象となる事業主
以下のすべてに当てはまる中小事業主が支給対象となります。
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること。
- 次のいずれかに該当する事業場を有する事業主であること。
- すべての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること。
- すべての対象事業場において、原則として、過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること。(※)
- すべての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
(※)基本的には1月45時間を超える時間外労働の実態があれば、要件を満たすこととなるため、問い合わせを行うことがおすすめです。
•勤務間インターバルを導入していない事業場
•既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
•既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
支給要件
以下のうち、いずれか1つ以上を実施することで支給対象となります。
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 人材確保に向けた取組
- 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 労務管理用機器の導入・更新
- デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
成果目標の設定
成果目標は、休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入し、定着を図ることです。
具体的には、事業主が事業実施計画において指定した各事業場において、以下のいずれかに取り組んでください。
- 新規導入
- 適用範囲の拡大
- 時間延長
上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。
助成金額・助成率
取り組みの実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じた金額が支給されます。
助成金額は、基本的に対象経費の合計額の3/4です。常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5となります。
ただし、上限額が設けられています。休息時間数や引き上げ人数などによって上限額が異なるため、詳細は助成金コンサルに確認もしくは厚生労働省のホームページを確認しましょう。
参考:厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」


働き方改革推進支援助成金 (団体推進コース)
働き方改革推進支援助成金 (団体推進コース)とは、「団体等の傘下である事業主の労働者の労働条件を改善するために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取り組みを実施した場合に、その事業主団体等に対して助成するコース」です。
このコースは、中小企業ではなく中小企業主の団体等を支援する制度です。
対象となる事業主
支給対象となる事業主団体等原則3事業主以上で構成(共同事業主においては10事業主以上)し、1年以上の活動実績がある事業主団体や共同事業主です。
こちらの詳細は、厚生労働省のホームページをご覧いただくかお問い合わせください。
支給要件
以下のうち、いずれか1つ以上を実施することで支給対象となります。
- 市場調査の事業
- 新ビジネスモデル開発、実験の事業
- 材料費、水光熱費、在庫等の費用の低減実験(労働費用を除く)の事業
- 下請取引適正化への理解促進等、労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整の事業
- 販路の拡大等の実現を図るための展示会開催及び出展の事業
- 好事例の収集、普及啓発の事業
- セミナーの開催等の事業
- 巡回指導、相談窓口設置等の事業
- 構成事業主が共同で利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の事業
- 人材確保に向けた取り組みの事業
成果目標の設定
成果目標は、支給対象となる取り組み内容について以下2つの達成を目指して取り組むことが求められています。
- 事業主団体等が事業実施計画で定める時間外労働の削減又は賃金引上げに向けた改善事業の取り組みを行うこと
- 構成事業主の2分の1以上に対してその取り組み又は取り組み結果を活用すること
助成金額・助成率
取り組みの実施に要した経費の一部を成果目標の達成状況に応じて、以下のいずれかのうち低い方の金額が支給されます。
- 対象経費の合計額
- 総事業費から収入額を控除した額(※1)
- 上限額500万円(※2)
(※1)例えば、試作品を試験的に販売し、収入が発生する場合などが該当します。
(※2)都道府県単位又は複数の都道府県単位で構成する事業主団体等(構成事業主が10以上)に該当する場合は、上限額1,000万円です。
参考:厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)」
働き方改革推進支援助成金の申請方法

働き方改革推進支援助成金を申請するには、どのコースでも管轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に「働き方改革推進支援助成金交付申請書」(様式第1号)(交付申請書)の提出が必要です。
以下の2通りの提出方法があります。申請期限を守って申請しましょう。
- 窓口へ申請書を持参
- 郵送で送付
提出後、労働局で基本的に1カ月以内に審査されます。
無事、交付が認められた場合、労働局から「働き方改革推進支援助成金交付決定通知書」(様式第2号)が発行されます。計画に沿って取り組みを実施し、交付決定の日から交付決定日が属する年度の1月31日までに改善事業を行いましょう。
取り組みが完了したら、再度労働局に支給申請を行って、助成金を受給します。


まとめ
働き方改革は今や社会的に求められている改革の一つですが、すべての企業が対応できる資金的余裕があるわけではないでしょう。そこで、働き方改革推進支援助成金の活用を検討してみてはいかがでしょうか。成果をあげることで、実施によって発生した経費の一部が支給される助成金となっています。
2025年度の申請受付はまだ発表されていないため、随時最新情報をチェックしてみてください。
また、助成金の基本知識について知りたい方は以下の記事をご覧ください。
関連記事:「助成金とは?注意点など知っておきたい基礎知識をわかりやすく解説!」