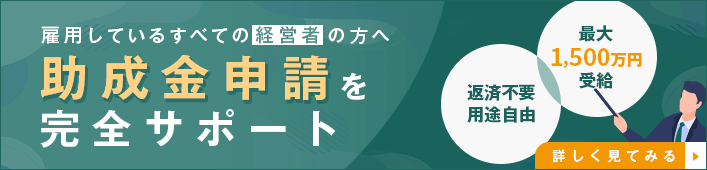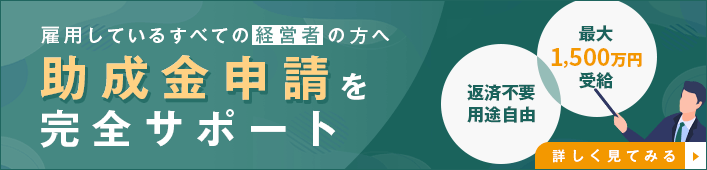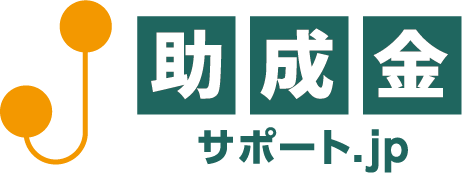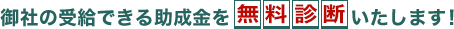2018年6月、参院本会議で働き方改革関連法が成立したことで、「長時間労働の是正」「高度プロフェッショナル制度」「同一労働同一賃金」の3つを柱とした、労働環境の改善が推進されることになりました。
労働者のニーズに即した公正で多様な働き方を実現し生産性や労働意欲の向上が図られるとともに、企業に対する罰則付き規制が増えます。それに伴い、同法が施行される2019年4月から2020年4月にかけて、企業には制度変更やシステム変更等の早急な対応が求められています。
労務違反の罰則化
長時間労働が大きな問題として取り上げられ、過労死や過労自殺といった命に関わる問題にまで発展しておきながら次々に明るみになる違法残業。
現在労働基準法で定められている労働時間は原則「1日8時間週40時間」ですが、36協定を結べば「月45時間年360時間」を上限に残業が認められています。
しかし、いわゆるブラック企業では残業が月100時間を超えるなど、法令順守には程遠い労働環境が敷かれており、これまで問題にはなっていたものの、大きな罰則もなく実質放置されてきました。
それが今回、改革関連法の成立により罰則化されることになったのです。
まだ解決すべき問題を抱えているものの、大企業では2019年4月から、中小企業でも2020年4月から施行されることになりました。これにより、一部劣悪とされていた労働環境も改善され、労働者のワークライフバランスに配慮した正常な働き方の実現が期待されます。
法の整備に伴い、具体的な動きも見られます。
根深く残る長時間労働問題に歯止めをかけるため、法改正を待たず労働基準監督署の体制が強化されるという記事が掲載されました。
記事によると、2018年度内に労働基準監督署の窓口指導員を5割程増員し、企業を訪問する指導員も1割近く増員することで、中小企業を中心に長時間労働是正の指導を強化する予定とのこと。指導員の増加により詳細なアドバイスができる体制を整え、一件当たりの相談に対し説明時間を十分確保することが狙いです。
それとともに、以前から人手不足が指摘されていた労働基準監督官の負担を減らし、労働基準法違反が疑われる事業所への立ち入り調査の強化を図る意向です。
是正指導を受けることのないよう、労働時間管理により長時間労働を抑制し、法令遵守の徹底が求められます。
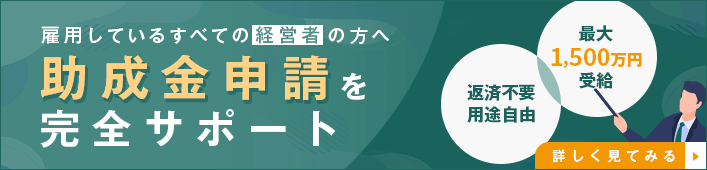
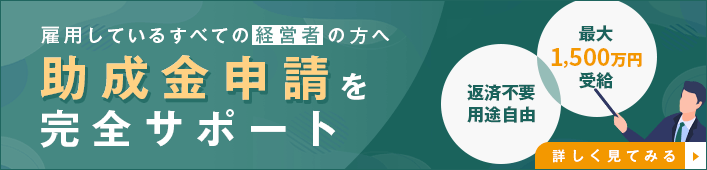
進まない企業の対応
行政の長時間労働対策が進む一方で、企業の対応はまだ十分とはいえない状況です。
株式会社ワークスアプリケーションズは、大手企業を対象に働き方改革関連法の成立に伴う対応状況調査を実施。
従業員の労働時間把握のために法定外総労働時間の集計をしていない企業は42%。休日労働時間を、法定内休日と法定外休日に分けて集計していない企業は43%と、半数に近い割合でした。
また、有給休暇取得日数が年5日に及ばない従業員が100人以上いる企業は40%。フレックスタイムの清算期間の上限を1ヶ月以上に定めるとした企業は2%、85%の企業では3ヵ月にはしないとしました。勤務時間インターバル制度を既に導入している企業は7%で、今後導入予定があると回答したのは1%にとどまりました。
調査結果から、企業の対応はまだ十分とはいえず、行政と現場、働き方改革と労働環境にはまだギャップがあることが伺えます。今後、このギャップを埋め意識をすり合わせることで、足並みを揃えていく必要があるのではないでしょうか。
「そもそも助成金って何?」「個人事業主でももらえるものなの?」という疑問をお持ちの方はこちら!助成金の制度や仕組みについてわかりやすく解説しています!
助成金とは?対象者や受給条件・申請の方法まで徹底解説今後求められること
労務違反の罰則化が進むとともに労働基準監督署が増員されたことにより、長時間労働の抑制が期待されます。これまで企業の労務違反に苦しめられた人にとっては、ようやくまともな職場になってくれるかもしれないという、安堵と期待があるのではないでしょうか。
しかし、法が整備されればすぐに環境が変わるとは考えにくいのも事実です。これまで何十年にもわたり日本で当たり前とされてきた働き方や意識を変えるのは一朝一夕で適うことではありません。
やり方を変えることで、当然弊害も考えられます。労働環境が馴染むまで、しばらくは企業の収益にも影響があるでしょう。また、働き方が変わることで個人の意識や社会のあり方も変化していくことが予想され、企業はそうした変化に対応し続けていくことが求められます。一度労働環境を変えたら終わりではないのです。
本来法令に従うのは最低限守らなければならないルールです。その上で求められるのは、さらに一歩進んだ労働環境の整備、時代の変化への適応です。
企業の利益のために個人の生活が犠牲になるような社会は、いい加減変えなければなりません。「ブラック企業」「過労死」などという言葉が過去のものとなるよう、社会全体で変化していくことが必要なのです。