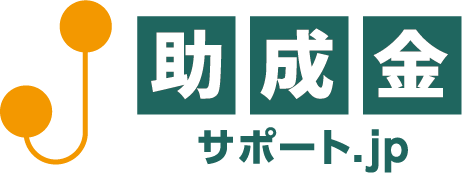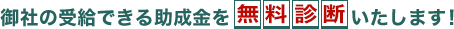農業の現場では人材不足の解消や業務効率化、品質向上のために、AIやスマート農機、6次産業化といった技術革新が進んでいます。こうした取り組みにかかるコスト負担を軽減するために、「ものづくり補助金」を活用することは、農業事業者にとっても大きなチャンスです。
しかし、「製造業向けでは?」「農業は対象外では?」と誤解している方も多く、せっかくの制度を活用できていない事例も見受けられます。
そこで、この記事では農業事業者向けに、ものづくり補助金の概要や支給要件、農業に関する活用事例をわかりやすく解説します。
農業にものづくり補助金は活用できる?
ものづくり補助金というと、名前の印象から製造業に関連する事業者が対象というイメージがあるかもしれません。しかし、農業にも、ものづくり補助金は活用できます。
ここでは、農業にものづくり補助金を活用するメリットやおすすめの活用方法を解説します。
農業にものづくり補助金を活用するメリット
農業にものづくり補助金を活用するメリットは、「コスト削減」と「作業効率化・生産性向上」の両方に取り組める点です。
人手不足や利益率の低さなどの経営課題に頭を悩ませている農業事業主は多いでしょう。問題を解決するには、従来のやり方を見直し、省人化・作業効率化・生産性向上につながる「経営革新」「新たな生産方式の導入」「新たな商品・サービスの開発」などが可能な機器・システムを導入する必要があります。
ものづくり補助金を活用することで、こうした設備投資にかかるコストを削減しながら、作業効率化・生産性向上を推進できるため、農業事業者におすすめの補助金なのです。
おすすめの活用「スマート農業」とは
ものづくり補助金のおすすめの活用方法の一つに、最近注目されているAI(人工知能)やロボット技術、IoTなどの先端技術を農業に取り入れる「スマート農業」が挙げられます。
- AI技術
AI技術を使用することで、作業の自動化や作業の効率化につながります。
例えば、AI搭載ドローンを活用することで、必要な場所への農薬散布や施肥が可能になるといった活用方法があります。 - IoT(モノのインターネット)
IoTとは、さまざまな機器をインターネットと接続して、データの収集や監視を行うことを指します。
スマート農業での活用例には、ハウス内にセンサーを設置し、土壌の湿度・温度などのデータを収集・解析することで、作物の最適な生育条件の把握などが挙げられます。 - ロボット技術
ロボット技術を使用することで、作業の自動化や作業の標準化につながります。
例えば、収穫ロボットや自動運転トラクターの導入などが考えられます。


ものづくり補助金とは
そもそもものづくり補助金とは、中小企業・小規模事業者などが取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援する制度です。
ものづくり補助金は、取り組み内容によって以下の2つの枠に区分されています。
- 製品・サービス高付加価値化枠:革新的な新製品・新サービス開発などの取り組みに必要な設備・システム投資を支援する枠
- グローバル枠:海外事業を実施して、国内の生産性を高める取り組みに必要な設備・システム投資などを支援する枠
海外事業に取り組んでいない農業事業者の場合には、上記のうち「製品・サービス高付加価値化枠」への申請が一般的です。
「製品・サービス高付加価値化枠」の補助率は、中小企業であれば経費の1/2、小規模企業・小規模事業者であれば経費の2/3(補助上限額3,000万円)と上限額が高額に設定されているため、農業に必要な機器・装置などの購入において大きな支援を受けられる可能性があります。
ものづくり補助金の各コースの詳細は、以下の記事をご覧ください。
関連記事:【2025年最新】ものづくり補助金とは?各コースを徹底解説
「そもそも助成金って何?」「個人事業主でももらえるものなの?」という疑問をお持ちの方はこちら!助成金の制度や仕組みについてわかりやすく解説しています!
助成金とは?対象者や受給条件・申請の方法まで徹底解説ものづくり補助金の対象となる農業事業者とは

ここでは、ものづくり補助金の対象となる農業事業者について解説します。
対象となる農業事業者
ものづくり補助金の対象となる農業事業者は、「資本金3億円以下」「常勤従業員数300人以下の法人または個人」である中小企業者・小規模企業者などです。
ここでいう常勤従業員数には日雇い労働者や季節労働者は含まれません。
対象となる取り組み
ものづくり補助金の対象となるには、以下の3つの基本要件をすべて満たす3~5年の事業計画を策定し、取り組む必要があります。
- 付加価値額の増加要件
事業者全体の付加価値額の年平均成長率(CAGR)を、3.0%以上増加させること - 賃金の増加要件
従業員や役員それぞれの給与支給総額の年平均成長率を 2.0%以上増加させること - 事業所内最低賃金水準要件
事業所内最低賃金を、毎年、事業実施都道府県における最低賃金より30円以上高い水準にすること
また、従業員数が21人以上の場合には、以下の要件も追加で満たさなければなりません。
- 従業員の仕事・子育て両立要件
「次世代育成支援対策推進法」第12条に規定する一般事業主行動計画の策定・公表を行うこと


ものづくり補助金の農業に関する採択事例

最後に、ものづくり補助金の農業に関する採択事例を紹介します。農業事業者の方は、ものづくり補助金の活用を検討する際の参考にしてください。
高級ブランド米「龍の瞳」の品質を高め売上高を2倍に
株式会社龍の瞳は、ブランド米「龍の瞳」を専門に扱う米の卸・販売会社です。
大粒ブランド米「龍の瞳」の割れ米を減らし品質向上を図るため、ものづくり補助金(令和2年度)を活用し、約3,500万円の精米ラインの導入、保冷倉庫設備を整備しました。
その結果、米のひびや割れ、劣化の防止に成功したことで、毎年10件以上あったクレームがほぼなくなり、出荷量が3年間で売上2倍に拡大。さらに超大粒米の商品化を実現するなど、多角展開を進めています。
| 事業計画名 | 精米ラインで日本の農業革新 ! 美味しい米づくりを田から工場へ ! |
|---|---|
| 主要製品 | 米 |
| 導入した設備など | 既存ラインに加えて導入した2列目の精米ライン(精米機、検査・選別に使用する色彩センサー、エア吸引式昇降機)の導入、付随する保冷倉庫 |
参考:令和6年度ものづくり・商業・サービス補助金成果活用「グッドプラクティス集」
新たな冷凍技術導入により、 余剰農産物の活用と長期安定供給の実現
株式会社京都義のは、国内最高級筍「白子筍」などの生産を京都最大規模で行っている会社です。
令和元年度補正ものづくり補助金を活用し、高速冷凍装置や真空脱気包装機など新たな加工設備を導入。
その結果、それまで廃棄されていた規格外野菜を活用し、冷凍食品として出荷することに成功しました。冷凍品が全売上に占める割合は約20%に達し、売り上げの底上げができました。また、3品目を製品化するなど新製品の開発に取り組めるようになりました。
人員増・コスト調整など課題を克服しながら、今後は京野菜を使ったミールキット開発など商品ライン拡充を目指しています。
| 事業計画名 | 新たな冷凍技術導入により、 余剰農産物の活用と長期安定供給の実現 |
|---|---|
| 主要製品 | 筍 |
| 導入した設備など | 冷凍加工機、真空脱気包装機、スチームコンベクションオーブン、急速液体凍結機、プレハブ冷凍の設備 |
参考:令和5年度ものづくり・商業・サービス補助金成果活用「グッドプラクティス集」
希少性の高い果実を使った新商品開発と商品ブランドへの取組み
有限会社農業法人清里ジャムは、カシス類などのスモールフルーツの栽培とジャム製品の製造に取り組んでいる会社です。
カシス類などスモールフルーツの加工を手がける事業者が少ないことから、加工事業へ進出しました。ものづくり補助金(2020年度)を活用し、製造に欠かせないミニ充填機と半自動キャッパーを導入。
これにより超低糖度ジャムと希釈タイプのフルーツコーディアルの2商品を開発できました。開発した商品が表彰されるなどの評価を受けたことで、バイヤーからの注目を集めることにも成功し、新たな販路拡大にもつながりました。
| 事業計画名 | 国産スモールフルーツを活用した新飲料等の商品開発と販路拡大事業 |
|---|---|
| 主要製品 | カシス類などのスモールフルーツとそのジャム製品 |
| 導入した設備など | 自動充填機、自動密封機など |
参考:令和2年度ものづくり・商業・サービス補助金成果活用「グッドプラクティス集」
まとめ
この記事では、農業事業者向けにものづくり補助金の活用メリットや支給要件、過去の採択事例を解説しました。
ものづくり補助金は、農業事業者も活用できる制度です。活用することで、新商品開発や販路拡大、生産性向上などにかかる費用負担を大幅に低減できます。
ものづくり補助金の受給を検討している農業事業主の方は、プロのコンサルタントへの依頼がおすすめです。採択される確率を高められるため、まず以下から無料相談を試してみてはいかがでしょうか。
無料相談はこちら