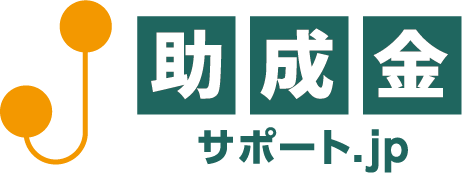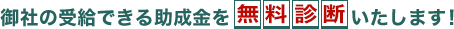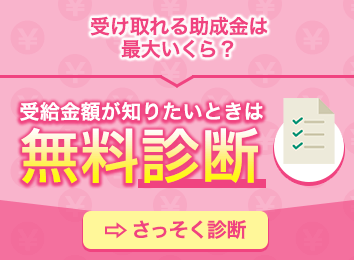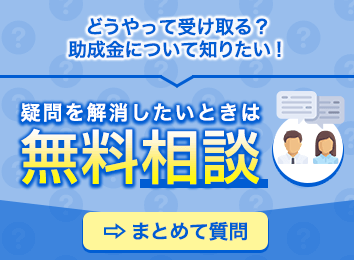戦略的創造研究推進事業 ALCA-Next
世界各国においてカーボンニュートラルの実現に向けた動きが加速し、GX(グリーントランスフォーメーション)関連投資も急速に拡大しています。GX の実現のためには、2050 年のカーボンニュートラルを実現するとともに、産業競争力の強化、経済成長・発展が必要不可欠です。今後の温室効果ガス(GHG)削減目標の達成や将来産業の創出に向けては既存技術の導入だけではなく新規技術の創出が必要であり、そうした技術を継続的に生み出すためには、産業界における実証や技術開発と並行してアカデミアにおける研究開発と人材育成への支援、企業とアカデミアの真の連携による社会実装が求められます。これに応えるため、科学技術振興機構(JST)は、「戦略的創造研究推進事業 ALCA-Next*1」(以下、本プログラムという。)並びに「革新的 GX 技術創出事業(GteX)*2」を 2023 年度より開始しました。
本プログラムは、カーボンニュートラルへの貢献という出口を明確に見据えつつ、個々の研究者の自由な発想に基づき、科学技術パラダイムを大きく転換するゲームチェンジングテクノロジー創出を目指します。具体的には、新規の原理・概念の創出やブレークスルーをもたらす要素科学・技術を対象とした基礎的な研究開発から、生み出された技術シーズを展開・拡大し、研究開発終了時には、研究開発成果の実用化が可能かどうか見極められる段階に至るまでの総合的な研究開発を推進します。
この目的を達成するために、「スモールスタート」「ステージゲート評価による選択と集中」「ステージゲート評価後の加速」等を特徴とした運営を行います。ステージゲート評価では、研究開発の継続/中止について、サイエンスとしての観点のみならず、本プログラムの趣旨である「カーボンニュートラルへの貢献可能性」という観点からも厳密な評価を行います。
また、本プログラムは、成果最大化のために、関係機関や関連事業との積極的な連携を図ります。特に、本プログラムの運営を統括するプログラムディレクター(以下、PD という。)が GteX の PDも兼任し、それぞれの事業の特徴を活かした積極的な連携を行うことで、早期実用化に向けた研究開発の加速を目指します。
本プログラムは、競争的研究費制度に該当します。
*1 ALCA-Next は、世界の潮流を先取りして 2010 年度から開始した「先端的低炭素化技術開発(ALCA)」における基礎研究支援の知見等を踏まえて、仕組みや特徴が設計されています。
*2 分野や組織を横断した全国のトップ研究者の連携体制をトップダウンで構築し革新的 GX 技術の創出を目指す事業です。詳細は事業 HP を参照 https://www.jst.go.jp/gtex/
対象者
研究開発提案者の要件
a. 研究開発代表者となる研究開発提案者自らが、国内の研究開発機関(民間企業や社団・財団法人等も含む)に所属して当該研究開発機関において研究開発を実施する体制を取ること(研究開発提案者の国籍は問いません)。
※以下の者も研究開発提案者として応募できます。
・ 国内の研究開発機関に所属する外国籍研究者。
・ 現在特定の研究開発機関に所属していない、もしくは海外の研究開発機関に所属している研究者等で、研究開発代表者として採択された場合、日本国内の研究開発機関に所属して研究開発を実施する体制を取ることが可能な者(国籍は問いません)。
※民間企業等の大学等以外の研究開発機関に所属している者も対象です。
b. 全研究開発期間を通じ、研究開発課題の責任者として研究開発課題全体の責務を負うことができる研究者であること。
(詳しくは「3.5 研究開発代表者及び主たる共同研究者の責務等」をご参照ください。)
c. 所属研究開発機関において研究倫理教育に関するプログラムを予め修了していること。または、JST が提供する教育プログラムを募集受付締切までに修了していること。
(詳しくは「4.1 研究倫理教育に関するプログラムの受講・修了について」をご参照ください。)
d. 以下の 4 点を誓約できること。
・ 「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成 26 年 8 月 26 日文部科学大臣決定)」の内容を理解し、遵守すること。
・ 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(令和 3 年 2 月 1日改正)」の内容を理解し、遵守すること。
・ 研究開発提案が採択された場合、研究開発代表者および研究開発参加者は、研究開発活動の不正行為(捏造、改ざんおよび盗用)ならびに研究開発費の不正使用を行わないこと。
・ 本研究開発提案書に記載している過去の研究成果において、研究活動の不正行為は行われていないこと。
研究開発体制の要件
a. 研究開発チームは、研究開発代表者となる研究開発提案者の研究開発構想を実現する上で最適な体制であること。
b. 研究開発チームに共同研究グループを配置する場合、共同研究グループは研究開発構想実現のために必要不可欠であって、研究目的の達成に向けて大きく貢献できること。
※ 共同研究グループを設置する場合は、グループに参加する研究者のうちグループを代表する者を指定し、「主たる共同研究者」としてください。研究開発グループ構成は、「研究開発担当者(研究開発代表者・主たる共同研究者)と同一の研究開発機関に所属する研究者のみによる構成」あるいは「その他の研究開発機関に所属する研究者等を加えた構成」のどちらでも構いません。「その他の研究開発機関に所属する研究者等を加えた構成」とする場合は、当該研究者から委託研究契約等で規定される事項(知的財産権の帰属等)が遵守されるよう同意書を得るなど適切に対応してください。ただし、研究開発機関から別の研究開発機関に(下図の場合、C 所属機関から D 所属機関に)再委託はできません。別の研究開発機関(下図の場合 D 所属機関)で委託研究開発費を執行したい場合は、主たる共同研究者として直接 JST と委託研究契約を締結する必要があります。募集要項「3.6 研究開発機関の責務等」もご参照ください。
※ 本プログラムの提案にあたっては、原則、海外の研究開発機関に所属する研究者にJST からの研究開発費の提供はできません。すなわち、海外の研究開発機関に所属する研究者を主たる共同研究者にすることは原則できません。
例外的に、研究開発構想実現のために海外の研究開発機関に所属する研究者が主たる共同研究者として参加することが必要不可欠であると認められた場合は、当該研究開発グループに JST から研究開発費を提供します。海外の研究開発機関を含む研究開発チーム構成を希望される場合には、研究開発提案書(様式 4-2:研究開発実施体制 2(FS 課題は FS 様式 4-2))に、海外の研究開発機関に所属する主たる共同研究者が必要であることの理由を記載してください。また、JST からの研究開発費提供を想定している提案においても、契約締結に至らなかった場合の当該グループとの連携案もあわせて研究開発提案書(様式 4-2:研究開発実施体制 2(FS 課題は FS 様式 4-2))に記載してください。これらの記載を基に、PO が書類選考の際に必要性を判断します。
加えて、海外研究開発機関は、原則として JST が提示する内容で研究契約を締結しなければなりません。なお、研究開発内容の特性等を勘案し、合理的な理由であると認められる事項については、契約条文を調整できる場合もありますが、調整期間は JST が交渉を開始してから原則 3 ヶ月までとさせていただきます。また、研究者ご本人が海外研究開発機関の契約担当者への説明等を行う必要が発生する場合があることも予めご了承ください。
海外研究開発機関の契約担当部局責任者の連絡先を研究開発提案書(様式 4-2:研究開発
実施体制 2(FS 課題は FS 様式 4-2)の特記事項)に記載の上、研究開発機関(契約担当部局責任者)として契約書の各条項について事前了承していることを示す所定の様式(海外研究開発機関向け/海外共同研究締結にあたっての事前確認書)を、面接選考会までに提出してください(選考過程で JST より問い合わせます)。
海外研究機関向け/海外共同研究締結にあたっての事前確認書
https://www.jst.go.jp/alca/dl/prior_confirmation.docx
「3.6 研究開発機関の責務等」もご参照ください。海外研究開発グループを含む研究開発
チーム全体の知的財産権等の成果の把握が可能であることもあわせて必要となります。なお、調整期間内に研究契約が締結できず連携案の実施も困難である場合には、研究開発不実施とします。
※ 海外機関用の委託研究契約書雛型等については、以下の URL よりご参照ください。
https://www.jst.go.jp/alca/dl/collaborative_research_agreement.pdf
研究開発機関の要件
研究開発機関は、研究開発を実施する上で、委託研究開発費の原資が公的資金であることを十分認識し、関係する法令等を遵守するとともに、研究開発を効率的に実施するよう努めなければなりません。「3.6 研究開発機関の責務等」に掲げられた責務が果たせない研究開発機関における研究開発の実施は認められません。応募に際しては、研究開発の実施を予定している研究開発機関に、確実に事前承諾を得てください。
支援内容
研究開発費(上限額)
以下を上限として、研究開発提案者が設定することができます。
・スモールフェーズ(1〜4 年目まで)は、上限 2,500 万円/年(直接経費)
・加速フェーズ(5〜7 年目まで) は、上限 7,500 万円/年(直接経費)
※ FS 課題(1〜2 年目)は、上限 250 万円/年(直接経費)です。
※ 選考の過程で、設定した研究開発費の妥当性を査定します。
※ 実際の研究開発費は、研究開発計画の精査・承認によって決定します。
※ 研究進捗状況等を踏まえ、研究開発期間中に別途調整する場合があります(詳細は、「3.1 研究開発計画の作成」を参照してください)。
※ JST は委託研究契約に基づき研究開発費(直接経費)および間接経費(直接経費の 30%が上限)を委託研究開発費として研究開発機関に支払います。
問い合わせ先
お問い合わせは電子メールでお願いします。
国立研究開発法人科学技術振興機構
未来創造研究開発推進部
E-mail: alca-next [at] jst.go.jp ※[at]を"@"に置き換えてください。