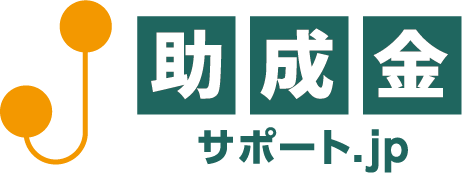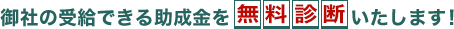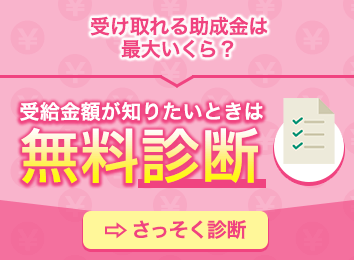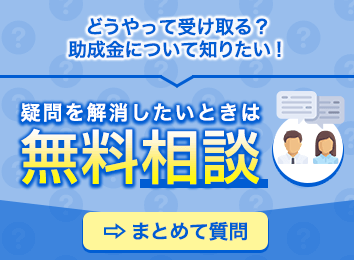訪問型職場適応援助者助成金
職場適応に課題を抱える障害者に対して、訪問型・企業在籍型職場適応援助者による支援を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。
また、助成金の支給対象期間が満了し、助成金の支給が終了した後も、対象となった障害者の雇用を継続するために必要な措置が実施できるよう努めてください。
対象者
障害者が職場に適応することを容易にするための訪問型職場適応援助者による援助の事業
を行う法人
支援内容
支給額
支給額は、次のイおよびロまでの助成金ごとに規定する額の合計額(以下「合計額」という。)とします。
また、1日の上限額の規定等については、「訪問型職場適応援助者の中高年齢等措置に係る助成金」を含めて適用されます。
イ 支援実施状況に応じた支給額
(イ)訪問型職場適応援助に係る支給額
訪問型職場適応援助に係る支給額は、一の支給請求対象期間に、支給請求を行う支給対象法人が配置する訪問型職場適応援助者が訪問型支援計画に基づき支援を実施した時間に応じて、次の a または b のいずれかに定める額にその回数を乗じた額の合計を、支給対象期間ごとに支給します。ただし、その額が1日につき3万6千円を超える場合は、3万6千円を上限とします。
なお、当該支給額等は令和6年4月以降の支援から適用します。
a 1回の支援時間(移動時間を含む)が4時間未満の支援、1回につき9千円
(精神障害者の支援を行った場合は、3時間未満の支援、1回につき9千円)
b 1回の支援時間(移動時間を含む)が4時間以上の支援、1回につき1万8千円
(精神障害者の支援を行った場合は、3時間以上の支援、1回につき1万8千円)
(ロ)移動時間
支援時間に含まれることとする移動時間については、原則として訪問型職場適応援助者が所属する事業所と支援の実施に係る事業所との往復および支援の実施に係る事業所間の移動に要した時間を計上するものとします。
また、支援の実施に係る事業所間の移動時間については、当該移動時間を2で除して得た時間数をその前後の支給請求に係る支援時間に含めることとし、訪問型職場適応援助者が自宅から支援の実施に係る事業所へ直行又は直帰する場合も、所属する事業所との往復とみなすものとします。
ロ 訪問型職場適応援助者養成研修に要した費用にかかる支給額
訪問型職場適応援助者について、以下の全てを満たす場合に、当該訪問型職場適応援助者の養成研修受講料(旅費・宿泊費等は対象外)として支給対象法人が支払った額の 2 分の 1 を、当該初めての支援を実施した日を含む支給対象期間の支給にあわせて支給します。
(イ)厚生労働大臣が定める研修受講修了後初めての訪問型職場適応援助を、当該訪問型職場適応援助者養成研修受講終了日から6か月以内に実施すること。
(ロ)支給対象法人が当該訪問型職場適応援助者養成研修受講料を全額負担していること。
ハ 事業実施施設の複数の訪問型職場適応援助者が、同一の支援対象障害者を支援する場合の支給額
次の(イ)から(ハ)までに掲げるとおりとします。
(イ)異なる日に支援を行っている場合は、複数の訪問型職場適応援助者が行った全ての支援が支給対象となること。
(ロ)同一日に支援を行っている場合は、複数の訪問型職場適応援助者のうち、1人分を支給対象とすること。
この場合、支援対象障害者に4時間以上の支援を行った訪問型職場適応援助者(支援対象障害者が精神障害者の場合は3時間以上)と4時間未満の支援を行った訪問型職場適応援助者(支援対象障害者が精神障害者の場合は3時間未満)がいる場合は、4時間以上の支援を行った訪問型職場適応援助者を優先して支給対象とすることができる。
(ハ)同一日に2人が支援を行っている場合であって、次のaからdの支援については、支援計画上それぞれ1回の支給対象とすることができる。
a 訪問型支援計画書の策定
b フォローアップ計画書の策定
c 地域センターが開催するケース会議への出席
d 総合センター及び地域センターが行う訪問型職場適応援助者のための支援スキル向上研修(以下「訪問型職場適応援助者支援スキル向上研修」という。)修了者と訪問型職場適応援助者養成研修修了者(修了後1年未満に限る。)がペア支援を行う場合(各研修の修了書(写)等を添付書類として提出)で、訪問型職場適応援助者養成研修受講後、最初の支援を行った日の属する支給対象期間に限り、8回まで認める。なお、4時間以上の支援(支援対象障害者が精神障害者の場合は3時間以上)と4時間未満の支援(支援対象障害者が精神障害者の場合は3時間未満)を併せて9回以上あれば、4時間以上の支援を優先して支給対象とすることができる。
ニ 複数の事業実施施設の訪問型職場適応援助者が、同一の支援対象障害者を支援する場合の支給額
次の(イ)から(ニ)までに掲げるとおりとする。
(イ)異なる日に支援を行っている場合は、複数の事業実施施設の訪問型職場適応援助者が行った全ての支援を支給対象とすることができる。
(ロ)同一日に支援を行っている場合は、同日に支援を行った訪問型職場適応援助者の支援を一の支援として、支援時間の合計に応じて支給額を算出し、それを同一日に支援を行った訪問型職場適応援助者の人数で除して得た額を、各訪問型職場適応援助者への支給額とする。
(ハ)上記(ロ)に係る支援と、別の支援対象障害者に対する単独での支援を同一日に行っている場合は、(ロ)に係る支給額と別の支援対象障害者に対する支援に係る支給額との和を、1日の支給額の上限の範囲内において、当該日の支給額とする。
(ニ)同一日に支援を行っている場合で、次のaからcの支援については、支援計画上2人まで、その人数で支給額を除すことなく計上することができる。
a 訪問型支援計画書の策定
b フォローアップ計画書の策定
c 地域センターが開催するケース会議への出席
補助金等との調整
法人が、(1)のイおよびロの助成金にあわせ、補助金等の支給額が確定している場合の助成金の支給額は、合計額から当該補助金等の額を控除した残りの額とし、当該補助金の額が合計額を上回るときは、助成金は支給しません。
支給期間
助成金の支給期間は、訪問型職場適応援助者が援助を行う期間のうち、7に規定する援助の事業の期間(支援期間)とします。ただし、支援対象障害者1人1回の援助につき最長1年8か月間(精神障害者は最長2年8か月間)を限度とします。この場合の1年8か月は、7に規定する集中支援期および移行支援期の期間を最長8か月、フォローアップの期間を最長1年間から成り、精神障害者にあっては必要に応じて追加のフォローアップ期間を最長1年間(訪問可能回数最大3回まで)とします。
ただし、支援対象障害者が支給期間の途中で、離職した場合(雇用が予定されていた事業所に就職しなかった場合を含む)、週所定労働時間を満たさなくなった場合、A型事業所の利用者となった場合等、支援対象障害者の要件を満たさなくなった場合は、この支援対象障害者に対する支援に係る支給は、当該変更のあった支給対象期間までとします。
問い合わせ先
助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。