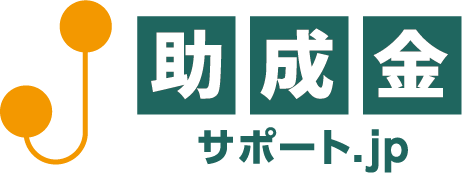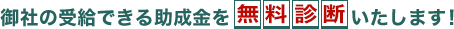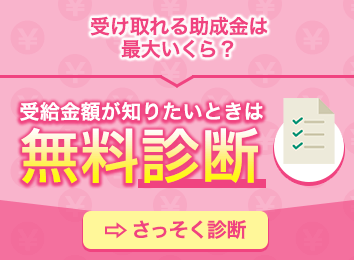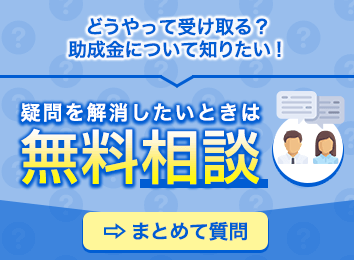障害者雇用納付金関係助成金(1-2⑨ 職場復帰支援助成金)
障害者雇用納付金関係助成金(以下「助成金」)は、障害者雇用納付金制度(『助成金の説明で使用される共通用語の解説』(以下「用語解説」といいます。)を参照)に基づき、事業主等への支援のために支給しています。このパンフレットで紹介している助成金は、支給対象となる障害者を雇い入れ、または継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を行う場合に支給します。
対象者
支給対象障害者
この助成金の支給対象事業主は次の(1)から(6)のすべてに該当する事業主です。
(1)支給対象障害者に対し、計画期間が1年以上の事業・支援計画を作成し、機構の受給資格の認定を受けていること
(2)支給対象障害者に対して、その職場復帰を促進するため、職場復帰の日(注釈)から3か月以内に職場復帰のための措置を開始し、休職等の期間中も含めて、常用雇用労働者としての雇用を継続する事業主であること
※休職等の期間中も継続して雇用保険に加入している必要があります。
(3)本助成金の申請に要する経費(意見書等の発行手数料)を全額負担する事業主であること
(4)支給対象障害者を、1回目の場合は1回目の支給請求対象期間の初日から6か月以上、2回目の場合は2回目の支給請求対象期間の初日から6か月以上の期間継続して雇用し、その支給対象障害者に対して、各支給請求対象期間分の賃金を支給した事業主であること
(5)支給請求時点において、支給対象障害者を解雇等事業主都合により離職させていないこと勤日をいいます。
(6)事業所において、次のイからハまでの書類を整備、保管していること
イ 出勤簿等、出勤状況を確認することができる書類
ロ 賃金台帳等の労働者に支払われた賃金を確認できる書類
ハ 離職した労働者の氏名、離職年月日、離職理由等を明らかにした労働者名簿等の書類
(注釈)出勤簿、タイムカード等により確認できる療養のための休職等に引き続く連続した休暇等の期間後最初の出勤日をいいます。
支給対象となる措置
中途障害者等に対して、職場復帰後の本人の能力に合わせて次の(1)または(2)の措置を講じる場合に支給の対象となります。
(1)時間的配慮等
次のイからハのいずれかに該当する措置を継続的に実施する場合
イ 労働時間の調整であって、次のいずれかに該当するもの(医師の意見書および支給対象障害者の同意の下に実施するものに限ります。)
(イ)勤務時間の変更(医師の意見書に具体的な勤務時間や短縮時間数等(注釈 1)が記載されていること)
休職以前に交替制等の勤務時間が不規則な勤務形態で勤務していた場合において、支給対象障害者の同意の下、医師が必要と認める場合に、当該交替制等の勤務を免除することを含みます。
(注釈 1)記載があいまい(最大●時間まで 等)で、措置との整合性が確認できない場合、計画を認定できないことがあります。
(ロ)通勤時間の短縮のための本人の転居を要しない勤務地の変更
支給請求時に実際の通勤時間が短くなっていることを確認します。
なお、休職の前に通勤していた支給対象障害者に対して、在宅勤務を職場適応の措置として実施する場合は、医師が必要と認めた場合に限り助成対象となります。
ロ 通院または入院のための、特別な有給の休暇の付与
就業規則等に規定する有給休暇制度以外の有給休暇を付与するもの(注釈 3)であって、医師の意見書に記載された必要な通院回数以上の通院回数が確保できるものに限ります。
(注釈 3)通院のための時間単位の特別な有給休暇を付与することも支給対象となります。
ハ 独居を解消し親族等と同居するための勤務地の変更
医師が必要と認め、支給対象障害者の同意の下に実施されるものに限ります。
職務開発等
次のイまたはロのいずれかに該当する措置を継続的に実施する場合
イ 外部専門家(注釈 4)の援助を得て行う職務開発(注釈 5)
ロ 外部専門家(注釈 4)による援助の結果、休職等の前に従事していた職務について実施できない業務がある場合に、これを踏まえた職種の転換(注釈 6)
(注釈 4)地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所その他の支給対象障害者を支援する障害者の就労支援機関の支援者を指し、医師、言語聴覚士等を含みます。
(注釈 5)障害の種類・程度等を考慮し、障害者の適性・能力等に適合する作業の開発または改善、作業工程の変更等を行う職場復帰のための措置をいいます。
(注釈 6)職業安定法第 15 条に基づき職業安定主管局長が作成する職業分類表(71 ページ参照)の中分類の異なる職務に就かせることをいいます。
支援内容
支給額
支給対象障害者1人あたり、下表に示す月額に、支給対象となるの月数(注釈 1)を乗じて得た額を支給します。
中小企業 支給月額:60,000 円
中小企業以外 支給月額:45,000 円
(注釈 1)就労していない月および支給対象障害者の出勤割合が6割に満たない月を除きます。
ただし、次のイからチまでに掲げる日は出勤日として取扱いますが、ニからチまでに掲げる理由により全休した対象月については出勤割合を満たさないものとします。
イ 受給資格認定を受けた事業所で所定労働時間の半分以上就労した日
ロ 出張した日(研修日を含む)
ハ 休日に出勤した日
ニ 人工透析のために勤務していない日または精神障害者にあっては主治医が指定する日に通院したことにより出勤していない日
ホ 労働基準法第 39 条に基づく年次有給休暇、年次有給休暇以外の法定休暇、同法第 65 条に定める産前産後の休業により出勤していない日
ヘ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に定める休業により出勤していない日
ト 慶弔による休暇、夏季休暇といった特別休暇等であって、就業規則または雇用契約書等に記載する休暇等により出勤していない日
チ 業務上の負傷または業務上の疾病にかかり療養のために出勤していない日
支給期間
支給期間は職場復帰のための措置を開始した日の直後の支給対象障害者の賃金締切日の翌日(注釈 3)から起算して最長1年間です。最初の6か月を1回目、次の6か月を2回目の支給請求対象期間といいます。
(注釈3)① 支給対象障害者の賃金締切日が措置開始日の場合は措置開始日の翌日から起算します。
② 支給対象障害者の賃金締切日の翌日が措置開始日の場合は当該措置の開始日から起算します。
(3)障害の種類に係る調整
イ 身体障害者
支給対象障害者 1 人に対して、一の障害の種類につき1回(最後の支給決定日の翌日から起算して4年間が経過しているものを除きます。)の認定に限り支給します。
ただし、次のイから二の分類により障害の種類が異なる場合には、この限りではありません。
身体障害の部位が次の(イ)から(ホ)までに掲げる分類を超えて異なるもの
(イ)視覚障害
(ロ)聴覚又は平衡機能の障害
(ハ)音声機能・言語機能又はそしゃく機能の障害
(ニ)肢体不自由
(ホ)心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害(ぼうこう又は直腸の機能の障害、小腸の機能の障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害及び肝臓の機能の障害)
ロ 精神障害者
精神障害に係る病名が次の(イ)から(ニ)までに掲げる分類を超えて異なるもの
(イ)統合失調症
(ロ)そううつ病(そう病、うつ病を含む)
(ハ)てんかん
(ニ)その他の精神障害
ハ 難病等にかかっている方
疾病名が異なる場合
二 高次脳機能障害のある方
原因となる事故等が異なり、かつ、当該事故等により従来の脳の機能的損傷の部位とは異なる部位の脳の機能的損傷のために、従来とは異なる高次脳機能障害の症状がある場合
問い合わせ先
助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。